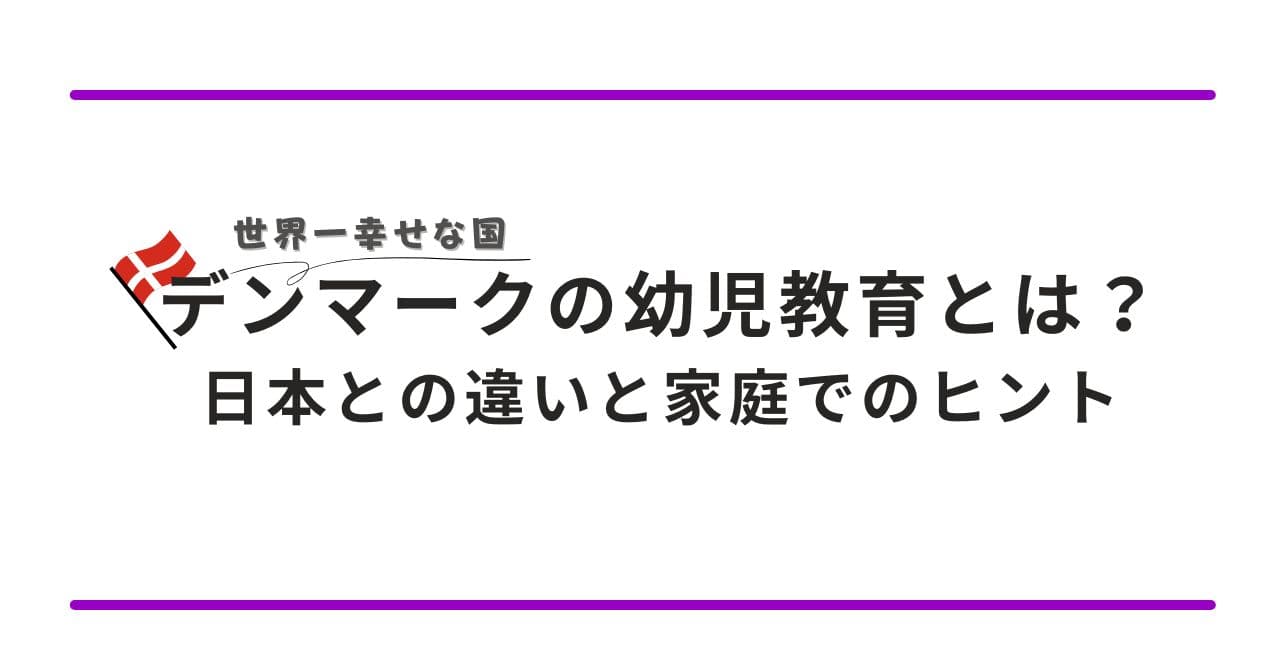あなたは、子どもの教育にどんな価値を求めていますか?知識を早く身につけること、集団生活に適応させること――それも大切かもしれません。
でも、北欧・デンマークの幼児教育では、まったく異なる視点が大切にされています。
なぜこの国の子どもたちは、伸びやかに、そして自信をもって育つのでしょうか?
本記事では、その秘密を紐解きながら、私たちの子育てや保育に生かせる視点を探っていきます。
答えは、意外なところにありました。
デンマークの幼児教育とは?|教育の目的と基本理念から見る子ども観

デンマークの幼児教育は、子どもを一人の「市民」として尊重し、自由と信頼に満ちた環境で成長を促すことを目的としています。
0〜6歳までの就学前教育では、国が定める枠組みをもとに各施設が独自のカリキュラムを作成し、子ども一人ひとりの発達や社会性を多面的に育む教育が展開されています。
ここでは、教育の根底にある価値観と、それを具体的に支えるアプローチを見ていきましょう。
教育は“生きる力を育てる”ためのもの
デンマークでは、幼児教育の最大の目的は「自立した市民を育てること」とされています。
知識の詰め込みや評価ではなく、子どもが自分の人生を選び取っていける力を育てることが重視されています。
保育カリキュラムでは、想像力や協調性、探究心などを育む6つの発達領域が設定されており、その成果はテストではなく日々の観察や記録で捉えられます。
また、施設は親との協働のもとで2年に1度カリキュラムを評価・更新する義務があり、常に子ども中心の質の高い教育が維持されています。
子ども自身が活動やルール決定に参加する場面も多く、小さな頃から「民主主義の練習」をしているのです。
これにより、自ら考え行動できる“生きる力”が自然と育まれていきます。
「遊び=学び」という考え方が根づいている
デンマークの幼児教育では、「遊び」は単なる余暇ではなく、最も重要な学びの時間とされています。
多くの園では一日の大半を自由遊びにあて、子ども自身が関心を持ったことに夢中になれる環境が整えられています。
教師はその中で子どもの気づきや対話を促す「伴走者」のような役割を果たします。
自然とのふれあいも非常に重視されており、森のようちえんのような形式では、雨の日でも外で過ごすのが当たり前。
虫や風、土といった自然要素が子どもの感覚や創造力を刺激し、結果的に知的好奇心や判断力も高まります。
このような「余白のある学び」は、日本のような時間割に沿った保育とは異なり、より深い探究や自己表現を可能にしているのです。
自己肯定感と社会性を育む土台づくり
子どもたちが自信を持って社会に関われるようになるために、デンマークの幼児教育では「自己肯定感」と「社会性」の育成が大切にされています。
そのための基盤となるのが、大人と子どもの信頼関係です。
保育士は「先生」として上から接するのではなく、名前で呼び合いながら対等な関係を築いています。
子どもの意見は尊重され、比較や過度な称賛は避けられ、行動の“プロセス”を丁寧に認めていく文化があります。
また、異年齢の子どもたちが一緒に活動することで、自然と助け合いの心やリーダーシップが育まれます。
失敗しても怒られるのではなく、「なぜそうなったか」を一緒に考える時間があり、自分の感情や考えを言語化する力も養われていきます。
こうした環境が、子どもたちの非認知能力や対人関係力の育成につながり、のちの人生にもよい影響を与えていくのです。
保育制度のしくみと支援体制|家庭と社会で子どもを育てる国

デンマークでは、子どもを育てることは家庭だけでなく社会全体の責任とされています。
そのため、保育制度や支援体制も家庭の多様な状況に対応できるよう、柔軟かつ包括的に整えられています。
年齢や家庭事情に応じた保育サービスが幅広く用意され、経済的・制度的なサポートも非常に手厚いのが特徴です。
ここでは、年齢別の保育施設の区分や、支援制度、そして保育の専門職「ペダゴー」の役割について詳しく見ていきましょう。
デンマークの就学前教育の年齢別区分(ナーサリー・幼稚園)
デンマークの就学前教育は、生後すぐから6歳までの子どもを対象に、年齢や発達段階に応じた施設で丁寧に行われています。
0〜2歳の子どもは「ナーサリー(Vuggestue)」または「家庭型保育(Dagpleje)」で、少人数の中で安心できる関係性を築きながら、生活習慣や感情表現の土台を育んでいきます。
3〜5歳になると「幼稚園(Børnehave)」へと進み、自由な遊びや集団活動を通して社会性や自己表現を伸ばします。
さらに6歳では義務教育前の「就学準備クラス(Børnehaveklasse)」に進み、小学校での学びにスムーズに移行できるようサポートを受けます。
| 年齢 | 施設名 | デンマーク語 | 主な目的・特徴 |
|---|---|---|---|
| 0〜2歳 | ナーサリー / 家庭型保育 | Vuggestue / Dagpleje | 安全な愛着形成、基本的生活習慣の習得、少人数の手厚いケア |
| 3〜5歳 | 幼稚園 | Børnehave | 自由遊びを中心とした学び、協調性や社会性、創造性の育成 |
| 6歳 | 就学準備クラス(プリスクール) | Børnehaveklasse | 小学校へのスムーズな移行、集団行動の慣れ、基礎的な言語・数の導入 |
このように、年齢ごとの発達段階に合わせた保育制度が体系的に整っており、子ども一人ひとりが安心して「自分のペース」で成長していける環境が保障されています。
日本のように「年齢で一律に切り替わる」制度とは異なり、子ども自身の“準備ができたタイミング”に合わせる柔軟性もデンマークらしい特徴といえるでしょう。
高福祉国家の支援内容(保育料、育児休暇、保育者配置)
デンマークが「子育てしやすい国」と称される理由のひとつが、保育に関する公的支援の充実です。
日本と比較すると制度設計そのものが「家庭と社会が協力して子どもを育てる」前提に立っている点が際立ちます。
デンマークでは、保育料は世帯収入に応じたスライド制で、上限が法律で定められています。
たとえば、どんなに所得が高くても、月額の支払いは最大でも費用全体の25%程度に抑えられており、ひとり親世帯や低所得世帯にはさらに補助が追加されます。 一方、日本も収入に応じた保育料制度を採用していますが、自治体ごとの差が大きく、「上の子が小学校に上がると負担が増す」などの声も多く聞かれます。
さらに待機児童問題の影響で、希望する保育園に入れないことも珍しくありません。 ・育児休暇制度
デンマークでは、両親合わせて約1年間の有給育児休暇が取得可能で、育児期間中の収入も国から補填されます。
加えて、父親の育児休暇取得率は約90%以上と高く、男女ともに育児に参加する文化が根づいています。 これに対し日本では、制度としては1年間の育休取得が可能ですが、取得率は母親が約8割に対し、父親は1〜2割程度にとどまっています(厚労省2023年調査)。
職場文化や周囲の目がハードルとなり、制度を活かしきれていない現状があります。 ・保育者の配置基準
デンマークの保育施設では、子ども3〜6人に対して1人の保育スタッフがつくことが法的に定められています。
この少人数配置により、子ども一人ひとりの個性や感情に寄り添うケアが可能です。 一方、日本では3歳児以上の配置基準が「20人に対して保育士1人」(2025年度からは一部改善予定)と、ヨーロッパ諸国の中でも最低水準に近いと言われています。
人手不足や長時間労働も重なり、保育士の負担が大きいのが実情です。
・デンマークは「保育料上限」「有給育休の補償」「手厚い人員配置」により、家庭が安心して子育てできる制度が整っている
・日本は制度があっても運用・文化面で課題が残り、親の負担感が大きい
・保育は「社会全体の責任」という考えが制度の土台にあるのがデンマークの特徴
「ペダゴー(pedagog)」の役割と保育士との違い
デンマークの保育現場で中心的な役割を担うのが、「ペダゴー(pedagog)」と呼ばれる教育・福祉の専門職です。
日本で言う「保育士」と似た職業ですが、実際の役割や求められるスキルには大きな違いがあります。
ペダゴーは単なる子どもの見守り役ではなく、子どもの社会的・感情的発達を支える教育者として位置づけられており、保育・教育・家庭・地域の連携までを包括的に担う存在です。
ペダゴーになるためには、大学で3年半にわたる専門教育課程(理論・実習・選択専門)を修了し、国家資格を取得する必要があります。
活動の中心は「遊びを通した学び」の設計や、子どもとの対話、発達に応じた支援、親との信頼関係づくりなど。
彼らは“社会に育てるプロフェッショナル”として、家庭や地域と連携しながら、子どもたちの人格形成を長期的に支えていきます。
| 項目 | デンマークのペダゴー | 日本の保育士 |
|---|---|---|
| 資格取得までの期間 | 大学(3年半)の学位+国家資格 | 専門学校(2年)または短大・大学で資格取得 |
| 位置づけ | 教育+福祉の専門職(準公務員扱い) | 保育・養護中心の職種 |
| 主な役割 | 遊びの設計、社会性・感情の支援、家庭・地域連携 | 生活支援、基本的生活習慣の育成、集団保育 |
| 担当する年齢 | 0歳〜成人まで(分野により) | 主に0〜6歳 |
| 働く場 | 保育施設、特別支援施設、青少年センターなど | 保育園、幼稚園、認定こども園 |
| 社会的な役割意識 | 小さな市民を育てる「教育者」 | 子どもの健やかな成長を見守る「保育者」 |
| 専門性の深さ | 教育・心理・福祉・社会学など多分野にまたがる | 保育・乳幼児教育中心 |
このように、ペダゴーは“保育+教育+福祉”を横断する包括的な専門職であり、子どもを個人として尊重しつつ社会の中で育てていくことを目的としています。
ペダゴーの存在は、デンマークの幼児教育の質の高さと子どもたちの幸福度を支える重要な要素のひとつです。
森のようちえんに学ぶ|自然との対話が育てる力

デンマークの幼児教育では、「自然とのふれあい」が子どもの健やかな成長に欠かせない要素とされています。
その象徴ともいえるのが「森のようちえん」と呼ばれる屋外型保育の存在です。
雨の日も雪の日も、子どもたちは自然の中で過ごし、五感を使って遊び、学び、生きる力を育てていきます。
ここでは、森のようちえんの基本的な考え方と、北欧で広がる文化的背景、そしてアウトドア保育がもたらす発達への具体的な効果を見ていきましょう。
雨の日も雪の日も外遊び|自然環境が教室になる
デンマークの森のようちえんでは、どんな天候でも子どもたちは外で遊びます。
雨が降れば水たまりを観察し、雪が降れば自分たちで雪だるまを作る。
そのすべてが「学びの素材」として活かされているのです。
「天気が悪いから室内へ」という概念はほとんどなく、むしろ自然の変化を体感することが子どもの五感や好奇心を刺激し、たくましさを育みます。
自然がそのまま教室となり、人工的な遊具では得られない体験が豊富にある環境です。
大人は安全面を見守るのみで、遊び方や目的を一方的に教えることはせず、子ども自身が考え行動する時間を尊重します。
このような環境で育った子どもは、自己判断力や忍耐力、挑戦する心を自然と身につけていくのです。
北欧で広がる「森のようちえん」文化とは?
「森のようちえん(Skovbørnehave)」は、1990年代にデンマーク全土で広まり、現在では保育選択肢の一つとして高く評価されています。
そのルーツはドイツにありますが、北欧では独自に発展し、環境教育・福祉・民主主義教育の視点が組み込まれたモデルとして認知されています。
特にデンマークでは、都市部から農村部まで多様な形態の森のようちえんが存在しており、公立・私立ともに運営されるのが特徴です。
共通しているのは、「自然を学びの場とする」という基本理念と、「子どもの主体性を尊重する」という保育姿勢です。
また、森のようちえんでは、年齢混合保育が多く、年上の子が年下の子を自然に助ける光景も日常的です。
これは社会性を育てる上でも大きなメリットとなり、北欧らしい共生の価値観が根づいています。
五感・創造力・自己判断力を育むアウトドア保育の魅力
森のようちえんの最大の魅力は、子ども自身が主体的に「感じて、考えて、動く」時間が圧倒的に多いことです。
たとえば、木の枝を拾って道具を作る、水たまりの深さを測って安全かどうかを判断する、鳥の鳴き声に耳を澄ませて季節を感じる──これらのすべてが、子どもの五感や創造性、そして論理的思考の土台を育ててくれます。
さらに、自然には正解も不正解もありません。
自分で試してみること、失敗してもまた挑戦することが当たり前の環境では、自己肯定感やレジリエンス(回復力)が自然と育まれます。
こうした非認知能力は、将来の学力や人間関係の土台になると言われており、教育先進国である北欧が森のようちえんを重視する理由のひとつとなっています。
都会的な教育とは異なる、自然と共に生きる力を育む教育のかたちは、これからの子育てに多くの示唆を与えてくれるはずです。
日本の幼児教育との違いは?|比較で見える“子どもを信じる文化”

日本とデンマークの幼児教育を比較すると、その根底にある「子ども観」の違いが浮かび上がってきます。
日本では「できることを増やす」教育が重視される一方で、デンマークでは「子どもを一人の市民として信じる」教育文化が広がっています。
特に、評価のあり方、しつけの捉え方、学びに対する姿勢において、対照的なアプローチが見られます。
ここでは、教育観の違いがどのように子どもの心や成長に影響するのかを紐解いていきましょう。
「評価しない教育」と「育てすぎない大人」
デンマークの幼児教育では、数値や成績による「評価」を基本的に行いません。
子どもたちは比較や競争にさらされることなく、自分のペースで遊びや生活に取り組むことができます。
一方で、日本の保育や幼児教育では、成果を見える形で記録し、発達を年齢基準で測る傾向があります。
また、デンマークの大人は子どもに過剰に介入せず、「子ども自身が気づくまで待つ」姿勢を大切にします。
子どものやる気や関心を尊重し、失敗も成長の一部として捉える文化が根づいています。
この“育てすぎない教育”は、子どもが自分を信じる力=自己効力感を育むうえで非常に有効です。
日本では、つい「教えすぎ」「手をかけすぎ」になりがちな大人の関わり方を見直すヒントが、デンマーク式の距離感にあると言えるでしょう。
しつけは“民主主義”のトレーニング
日本における「しつけ」は、しばしば「大人のルールに子どもを従わせること」と捉えられがちです。
「ダメなものはダメ」「これはこうするもの」といった形で、正解を一方的に伝え、大人がリードする構図になりやすいのが実情です。
一方で、デンマークでは“しつけ”そのものが、民主主義の練習とされています。
トラブルや失敗が起きたとき、大人はすぐに正解を与えるのではなく、「どうしてそう思った?」「相手はどう感じたかな?」と問いかけ、子ども自身に考えさせるのです。
このように、対話と納得を通じて行動変容を促す姿勢は、他者を尊重しながらも自分の考えを持つ「共生する力」の育成に直結しています。
| 観点 | 日本のしつけ | デンマークのしつけ |
|---|---|---|
| 基本姿勢 | 大人がルールを与え、子どもを従わせる | 対話と納得を重視し、子どもに考えさせる |
| トラブル対応 | 叱責やルールの再提示で制止 | 質問と対話で状況を振り返らせ、気づきを促す |
| 主体性の扱い | 受け身にさせがち | 自分の感情や理由を言葉にすることを促す |
| 教育的ゴール | 社会のルールを守れる子ども | 他者と共に生きる力・内発的な判断力を育てる |
| 大人の関わり方 | 指示・命令中心 | ファシリテーターとしての支援 |
デンマークのこの「信じて任せるしつけ」は、子ども自身が社会の一員として「自分で考え、責任を持って行動する」力を養う土壌をつくっています。
日本のように「従わせるしつけ」に疑問を感じている保護者や保育者にとって、子どもを一人の主体として扱うことの大切さを改めて考えるきっかけになるでしょう。
詰め込み・先取り教育との距離感
近年の日本では、早期教育や先取り学習が注目され、「小学校に入る前にできるだけ多くの知識や技能を身につけさせたい」という風潮があります。
英語教育や計算、読み書きの先取りなどがその一例です。
一方、デンマークでは幼児期の学習に“早さ”や“正確さ”を求めることはほとんどありません。
むしろ、「今、その子が何に関心を持っているか」「どんなふうに世界を感じているか」に焦点を当て、遊びや対話を通じてゆるやかに学びが深まっていくプロセスを大切にしています。
学力ではなく、「好奇心」「想像力」「試行錯誤する姿勢」など、学びの土台となる“非認知能力”に目を向けているのが特徴です。
結果的に、そうした力は後の学業や社会生活でも強みとなり、子ども自身の「学びたい」という気持ちを長く保ち続けることにつながっています。
日本でも、急がず焦らず、学びの本質に立ち返る必要があるのかもしれません。
家庭で取り入れるデンマーク式子育てのヒント
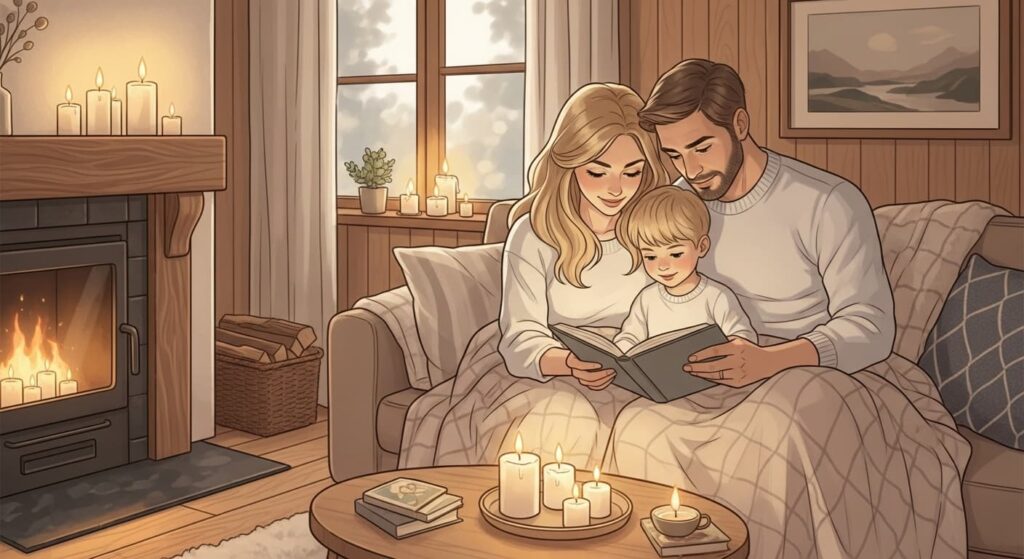
北欧の高福祉社会で育まれたデンマークの子育てには、子どもとの関係性を深め、無理なく自己肯定感を育むためのヒントが詰まっています。
「すぐには真似できない」と思われがちですが、実は家庭でも今日から取り入れられる考え方や習慣が多くあります。
ここでは、子どもの主体性を尊重するコミュニケーション、親子で過ごす心地よい時間のつくり方、そして非認知能力を育む遊びの工夫を紹介します。
「やらせる」ではなく「選ばせる」子育て
デンマークの子育てでは、「子どもに自分で選ばせること」が日常の中に根づいています。
たとえば「どの服を着たい?」「今日は何して遊ぶ?」といった問いかけを通じて、子どもが自分の意思で選択し、それに責任を持つ感覚を自然と身につけていくのです。
日本ではつい「早くして」「こうしなさい」と指示を出してしまいがちですが、デンマーク式では“待つこと”や“見守ること”が親の大切な役割とされています。
失敗しても大人がすぐに口を出さず、子どもが自分で気づくまで待つ。
その繰り返しが、自己決定力や問題解決力を育てる基礎になります。
日常の小さな選択肢を子どもに任せるだけで、「信じてくれている」という実感を子どもは感じ取るのです。
ヒュッゲ(Hygge)のある暮らしと親子の時間
「ヒュッゲ(Hygge)」は、デンマーク語で“心地よさ”や“穏やかな幸福感”を意味する言葉です。
家庭でヒュッゲを大切にするということは、家族が安心してリラックスできる時間を意識的につくるということ。
たとえば、キャンドルを灯して一緒にお茶を飲む、絵本を読む、テレビを消して会話を楽しむなど、特別なことではなく、日常の中の“親密なひととき”を大切にします。
このような時間を持つことで、子どもは「自分は大切にされている」と感じ、情緒の安定につながります。
また、親にとっても忙しい毎日の中で立ち止まり、子どもの表情や気持ちに目を向けるきっかけになります。
日本でも、1日10分でも“スマホを置いて向き合う時間”を意識するだけで、ヒュッゲのエッセンスを暮らしに取り入れることができます。
ごっこ遊び・対話のある日常で育む非認知能力
デンマークの保育現場では、自由な「ごっこ遊び」がとても重要視されています。
ごっこ遊びは単なる“遊び”ではなく、子どもが自分の役割を考え、他者と関わりながら想像力や言語力、社会性を育てる絶好の機会です。
たとえば、店員さんとお客さんになってやりとりをする中で、順番を待つ、相手の気持ちを察する、自分の言いたいことを伝える――そうした経験が、非認知能力(思いやり・がまん・創造性など)を自然と育てていきます。
家庭でも、ぬいぐるみを使った簡単なやりとりや、親子でのごっこ遊びは効果的。
さらに「今日はどんな一日だった?」「うれしかったことはあった?」といった問いかけを日常的に行うことで、子どもは自分の感情を整理し、表現する力を伸ばしていきます。
非認知能力は、知識やスキル以上に、人生を前向きに生きる力の土台となるもの。
デンマーク流の“遊びと対話”は、それを無理なく育む方法のひとつなのです。
保育士・教育関係者が注目するデンマーク教育の実践事例

デンマークの幼児教育に対する関心は、保護者だけでなく、日本の保育士や教育関係者の間でも年々高まっています。
特に「ペダゴー(pedagog)」の理念に基づいた実践や、遊びを通じて非認知能力を育む北欧式アプローチは、多くの保育現場に新たな気づきをもたらしています。
ここでは、日本国内で広がるデンマーク式教育の導入例、人材育成への応用、そして実際の現場での変化の声を紹介します。
保育現場で広がる「北欧式アプローチ」導入例
日本国内のこども園や保育園の中でも、近年「北欧型の保育手法」を取り入れる施設が増えています。
たとえば、東京・静岡・三重などでは、フィーノリッケの研修を受けた園が「対話を中心にした保育」「遊びから学ぶ時間設計」「自然とのふれあいの導入」などを実践し、子どもの主体性を伸ばす保育にシフトしています。
また、1日のスケジュールを柔軟に変更できるようにし、「今日は何して過ごしたい?」という問いかけから子どもの一日を始める園も登場。
先生たちもファシリテーターとして関わることで、子どもとの関係性がより対等で豊かになったという報告もあります。
こうした北欧式アプローチの導入は、学力や行動の型にはめるのではなく、“その子らしさ”を引き出す保育のあり方として注目されています。
デンマーク式アプローチを取り入れている日本の保育施設(こども園・保育園)を参考にした、導入園の「1日のスケジュール例」をご紹介します。
北欧教育の理念に基づき、「時間にしばられすぎない」「子どもの主体性を尊重する」構成が特徴です。
スケジュールはあくまで目安であり、天気・子どもの気分・興味関心によって柔軟に変化します。
北欧式アプローチ導入園の1日スケジュール(例) |
||
|---|---|---|
| 時間帯 | 活動内容 | 特徴・ポイント |
| 7:30〜9:00 | 登園・自由遊び | 子どもが来た順に受け入れ。園庭・室内で思い思いに過ごす |
| 9:00〜9:30 | 朝のサークルタイム(対話・確認) | 子ども主体の「今日は何して過ごしたい?」対話から1日がスタート |
| 9:30〜11:30 | 遊びの時間(屋外・森・公園など) | 自由遊び中心。自然の中での探索・ごっこ遊び・ものづくりなど |
| 11:30〜12:00 | 帰園・昼食準備 | 子どもたち自身でテーブル準備や配膳を行う(生活力育成) |
| 12:00〜13:00 | 昼食 | 食事中も「会話」を大切にする。“静かに食べる”は強制しない |
| 13:00〜14:30 | 午睡 or 静かな時間 | 寝る・読書・お絵描きなど、子どもが自分に合った休息方法を選べる |
| 14:30〜15:00 | 起床・おやつ | 起きる時間も子どもの様子に合わせて柔軟に対応 |
| 15:00〜16:00 | 遊びと振り返りの時間 | 朝の活動の続きを行ったり、1日をふりかえる対話(感情表現・自己認知) |
| 16:00〜18:30 | 降園・自由遊び | 保護者のお迎えまで、ゆったりと好きな遊びを楽しむ |
・スケジュールより「子どもの状態」を重視:時間が来たから終わらせるのではなく、集中しているときは活動を続けさせる ・「話し合う力」を日常の中で育む:朝・帰りのサークルタイムで気持ちや考えを共有 ・“活動させる”より“環境を整える”:大人は教えるのではなく、興味が広がるような空間づくりに徹する
このような1日を通して、子どもは「自分で選び、自分で決めて、自分で動く」経験を繰り返し、主体性や感情のコントロール、他者との関係性を学んでいきます。
ペダゴーをモデルにした人材育成と講座
保育現場の質を高めるうえで注目されているのが、「ペダゴー」をモデルにした人材育成です。
日本では、フィーノリッケなどの教育機関が中心となり、ペダゴーの理念に基づいた研修プログラムや講座が各地で開催されています。
これらの講座では、デンマークで行われているように、「子どもとの信頼関係づくり」「遊びの設計」「保護者との対話の技法」などを理論とワークショップを通じて学ぶことができます。
また、実際にデンマークの保育園を視察するプログラムもあり、日本の教育者が現地の空気を肌で感じながら学びを深める機会も増えています。
こうした人材育成は、従来の「管理・指導型保育」から脱却し、「共に育ち合う関係性」を大切にする保育者を育てる大きな転機となっているのです。
教育現場の声|「先生たちが変わった」体験談
デンマーク式のアプローチを導入した現場からは、「子どもが変わった」だけでなく、「先生たちが変わった」という声も多く聞かれます。
たとえばある保育園では、「これまで“指導しなきゃ”と思っていた先生が、子どもを“信じて見守る”ことを学んだ」といった変化がありました。
子どもとの関わりが命令型から対話型に変わることで、先生自身が子どもを「小さな大人」として尊重できるようになり、保育がより楽しくなったという実感も広がっています。
また、日々の保育の中で「正解を求めすぎない」姿勢が定着し、失敗や葛藤をそのまま受け止めて話し合う文化が育まれつつあります。
これはまさに、デンマークで大切にされている“信頼と対話を基盤にした教育”が、日本でも少しずつ根づき始めている証拠だと言えるでしょう。
デンマーク教育をもっと知るためのイベント情報

学びを深めたい保育士・教育関係者、そして自宅での実践を志す保護者に向けて、デンマーク教育を日本でも体感し、学べる情報を集めました。
ここでは、ペダゴー関連の国内講座、現地視察プログラム、そして森のようちえんを体験できるツアーをご紹介します。
日本でも学べる!ペダゴー関連講座・イベント紹介
日本では、ペダゴーの思想や実践を体系的に学べる講座が充実しています。
たとえば「一般社団法人ペダゴージャパン」では、デンマーク発の教育アプローチを10日間で学ぶ資格認定講座を開講しています。
対話やウェルビーイング、多様性への理解など、ペダゴーの視点を実践できるスキルを培う内容となっています。
また、北欧教育専門の「フィーノリッケ」では、入門・ベーシック・アドバンスの3段階講座が提供されており、保育現場や家庭現場でデンマークの教育理論・実践を活かすためのカリキュラムが整っています。
どちらも教育関係者や保護者を対象に開催され、自宅でも活かしやすい内容となっているため、「まずは理論を知りたい」「実践のヒントを得たい」方には最適です。
教育視察プログラム・森のようちえん体験ツアー
実際にデンマークの現場を体感できる視察プログラムも人気です。
「ノルディック・インスピレーション」と「森のようちえん全国ネットワーク連盟」が主催する森のようちえん体験付き視察ツアー(2025年8月開催予定)では、コペンハーゲン近郊の森のようちえんボンサイで3日間インターンし、公立園や特別支援学校なども見学できます。
プログラムには事前講義やオンラインオリエンテーションが含まれており、実際に保育現場に参加する中で「対話」と「観察」を重視した保育の感覚を身につける設計です。
また別途、7日間の視察ツアーもあり、森型と都市型施設を連続して訪問し、両方の違いを比較できる内容となっています。
「幸せの土台」を育むデンマークの幼児教育から学べること

デンマークは「世界一幸福な国」として知られていますが、その背景には、子どもの頃から社会に大切にされ、自由と信頼の中で育つ環境があります。
幼児教育もまた、知識の詰め込みではなく「心の豊かさ」や「自分らしさ」を育てることに重点が置かれており、これが人生全体の幸福感につながっているのです。
私たち日本の親や教育関係者にとっても、そこには日々の関わり方を見直すヒントが多く詰まっています。
ここでは、デンマークの教育から学べる“幸せの土台づくり”のエッセンスを2つの視点から振り返ります。
自由・信頼・対話がつくる心の豊かさ
デンマークの幼児教育が目指しているのは、「自分を大切にし、他者とも平和的に関われる人」を育てることです。
そのために重視されるのが、自由・信頼・対話の3つの柱。
子どもは自分のペースで遊び、考え、選択し、時には失敗も経験しながら成長していきます。
大人はそれを管理せずに“信じて見守る”ことで、子ども自身が「自分で考えていいんだ」「失敗しても受け入れてもらえる」と感じる環境が生まれます。
また、日々の保育や家庭生活の中では「一方的に叱る」のではなく、対話を通じて感情や意見を整理することが基本です。
このような関わりは、心の安定や自己肯定感を高め、結果的に「幸せを感じる力」を育てていきます。
日本の教育や家庭に生かせる“北欧流のまなび”
デンマークの教育から学べることは、決して特別な制度や文化だけではありません。
大切なのは、子どもを信じて任せる姿勢、結果より過程を大事にする考え方、そして家庭の中に安心できる空間をつくることです。
たとえば、選ばせる子育て、小さな“ヒュッゲ(心地よさ)”の時間、対話を大切にする日々の関わり――こうした取り組みは、日本の家庭でも無理なく始められるものばかりです。
また、保育や教育の現場では、子どもに「決まった正解を求めすぎない」こと、そして「今ここでの体験や関係性を育てること」にもっと焦点を当てることで、子どもたちの本来の力がより自然に育まれていきます。
効率や成果を求める現代の子育てにとって、デンマークのような“ゆるやかで、でも深い教育”は、心に余白を与えてくれる視点になるのではないでしょうか。
関連コラム
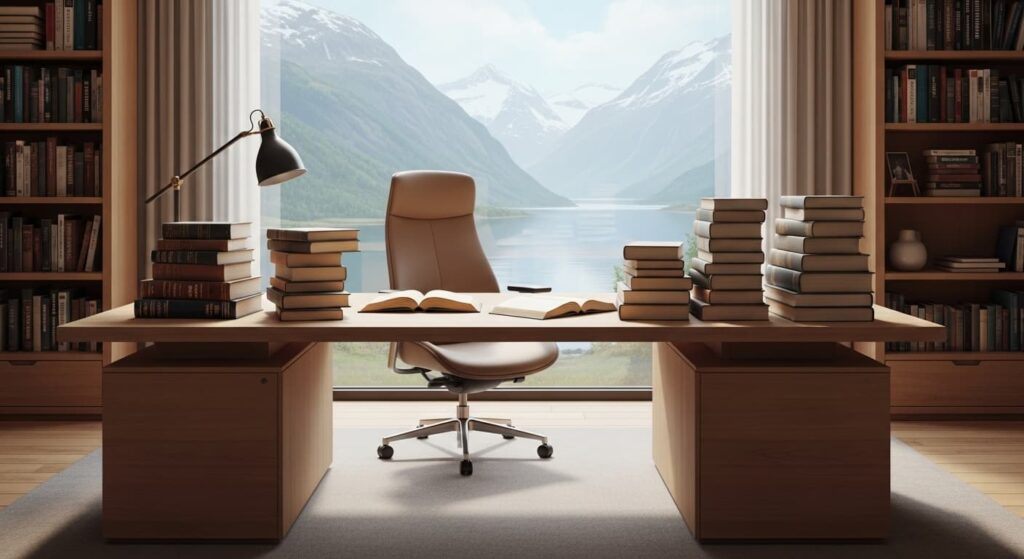
以下の記事は、教育法や親子コミュニケーションに関する知見が豊富で、本記事のテーマと親和性が高い内容です。
おすすめ書籍|『北欧の森のようちえん 自然が子どもを育む』
自然との関わりが子どもの成長に与える影響を、デンマーク・シュタイナー幼稚園の実践を通じて学べる本です。
家族で自然遊びを取り入れたい方や教育者にも特におすすめです。 書籍紹介
『北欧の森のようちえん 自然が子どもを育む』(リッケ・ローセングレン著、ヴィンスルー美智子・村上進 訳) 自然を教室に変えるデンマークのシュタイナー幼稚園「こども島ボンサイ」が実践する保育のノウハウを、写真とともに詳細に紹介。 写真集のように美しいビジュアルとともに、感覚を刺激する遊びの仕掛けや、自然の中で育む社会性・判断力・レジリエンスのエッセンスが学べます。
家庭での自然育児や、教育現場への導入を考えている方にぴったりです。
価格:約2,970円(Amazon)