情報があふれる今、「どの幼児教育メソッドがうちの子に合うのか」「本当に効果があるのか」と迷う親は少なくありません。
本ガイドは、発達心理学・脳科学・教育経済学の知見を土台に、主要メソッドをわかりやすく比較し、家庭の状況に合わせた“失敗しない選び方”と費用対効果の見方まで具体的に解説します。
実証研究と情報へのリンクを明示し、明確なエビデンスに基づいてお伝えします。ぜひご覧ください!
はじめに|なぜ今「幼児教育メソッドの選択」が重要なのか?
 選択肢が増えた現代の子育てでは、まず「何を基準に選ぶか」を決めることが大切です。
選択肢が増えた現代の子育てでは、まず「何を基準に選ぶか」を決めることが大切です。
本章では、2025年の最新動向を踏まえ、幼児教育メソッドの全体像と選び方の判断軸(比較ポイント)をわかりやすく整理します。
親が悩む幼児教育メソッド選び
親が幼児教育メソッドの選び方に悩む背景には、情報過多と宣伝の混在があります。
SNSや口コミ、広告が交錯し、「モンテッソーリ」「シュタイナー」「STEAM」など名称だけが独り歩きしがちです。
さらに共働き世帯の増加で使える時間は限られ、費用対効果への関心も高まっています。だからこそ、理想論ではなく根拠ある選択軸が必要です。
重視すべきは、メソッド名よりも「年齢に合っているか」「主体的に学べるか」「家庭で無理なく続けられるか」です。
学びの成果は、関わり方・環境・振り返りといったプロセスの質によって大きく変わります。
OECD(経済協力開発機構)のレビューも、カリキュラムや研修、集団規模、評価・モニタリングなど“プロセスの質”が要と指摘しています。
脳科学・心理学が示す「幼児期の投資」の大きなリターン
“早い者勝ちの詰め込み”ではなく、幼児期にふさわしい関わりと環境への投資が、学び続ける力・社会性・健康などに長期の恩恵をもたらします。ハーバード大学の開発科学センターは、養育者との「サーブ&リターン(呼びかけ→応答の往復)」が脳の基盤形成を支えると解説しています。家庭でも今すぐ実践できる具体的ステップが提示されています。
また、質の高い就学前教育への投資は年率7〜10%の社会的収益を生むと推計されてきました(ペリー就学前計画などの費用便益分析)。短期のテスト点ではなく、生涯所得・健康・社会適応といった“広い成果”で評価されます。
引用:ハーバード大学>Center on the Developing Child>5 Steps for Brain-Building Serve and Return Copy
HCDC Pediatrics>Early Brain and Childhood Development
ペリー就学前プログラムの収益率
The Heckman Equation>Getting down to business
on early childhood development.
幼児教育の基礎知識|発達心理学から見る「早期教育との違い」
 幼児教育とは、0〜6歳の子どもを対象に、遊びや生活を通じて「心・体・ことば・社会性」をバランスよく育てる教育を指します。
幼児教育とは、0〜6歳の子どもを対象に、遊びや生活を通じて「心・体・ことば・社会性」をバランスよく育てる教育を指します。
発達心理学では、この時期は好奇心・主体性・非認知能力(集中力や自己調整力)が大きく伸びる時期とされています。
一方で早期教育は、就学以降に習う知識や技能(読み書き・計算など)を前倒しで教えるアプローチです。
短期的には成果が見えやすい反面、年齢や発達に合わない“先取り学習”は、子どもの意欲や創造性を損なうリスクもあります。
心理学的に見ると、幼児教育は「内発的動機づけ」「遊びを通じた学び」「全人的発達」を重視し、長期的な人格形成につながります。
対して早期教育は「外発的動機」「短期的な成果」「技能の先取り」に偏りがちです。
この違いを理解しておくことで、子どもに無理をさせず、発達段階に合った最適なメソッドを選ぶ基準が見えてきます。
幼児教育とは?早期教育との決定的な違い(全人的発達 vs 先取り)
幼児教育と早期教育の最も大きな違いは「子どもの心理的な育ち」に表れます。
実際にアメリカの大規模なプリK(就学前教育)研究では、入学当初は点数が上がっても、質の高い環境や小学校以降との継続的な学びが伴わない場合、その効果は数年で薄れると報告されています。
つまり大切なのは、「早ければ良い」のではなく、子どもの年齢・発達段階に合った方法を選び、主体性を支える学びを積み重ねることです。
脳発達の節目(3歳・6歳)と学びの関係
乳幼児期は神経回路が爆発的に張り巡らされる時期です。
丁寧な相互作用(サーブ&リターン)と、試行錯誤できる環境が「注意・抑制・ワーキングメモリ」など実行機能の土台をつくります。
年齢が上がるほど回路の可塑性は徐々に下がるため、“今この年齢に合う刺激”が要です。
日本のカリキュラム「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」
文部科学省は、就学前までに育みたい資質や能力を、次の「10の姿」として示しています。
②自立心
③協同性
④道徳性・規範意識の芽生え
⑤社会生活との関わり
⑥思考力の芽生え
⑦自然との関わり・生命尊重
⑧数量/図形/文字等への関心・感覚
⑨言葉の伝え合い
⑩豊かな感性と表現
園選びやメソッド選択の“共通ものさし”として活用しましょう。
引用:文部科学省>幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
主要メソッドを一気に比較|代表的なアプローチ
 海外で確立された代表的メソッドを、理念・学びの進め方・向き不向きの観点で掘り下げます。
海外で確立された代表的メソッドを、理念・学びの進め方・向き不向きの観点で掘り下げます。
名称だけで選ばず、家庭との相性まで見えるよう要点を比較し、それぞれのメソッドの特徴を見ていきましょう。
| メソッド | 特徴 | 向いている子ども | 心理的効果 |
| モンテッソーリ | 環境と教具で自主性を育成 | 集中・秩序好き | 自立心・集中力 |
| シュタイナー | 芸術・リズム重視 | 想像力豊か | 感性・創造性 |
| レッジョ | プロジェクト型探究 | 好奇心旺盛 | 協調性・探究心 |
モンテッソーリ教育|自己教育力と集中を育てる環境設計
モンテッソーリ教育では、子どもが自分で選び、手を動かし、集中してやり切るための「準備された環境」を整えるのが核です。
専用教具と縦割りクラスで子ども一人一人のペースを尊重します。
向いているのは、一人でコツコツ取り組むのが好き、秩序感が心地よいタイプの子どもです。内発的動機づけや自立心の育成に強みがあります。
シュタイナー教育|生活リズムと芸術体験で感性を育む
シュタイナー教育では、自然素材の教材、手仕事、音楽・芸術など“体験と模倣”を重視しています。
0〜7歳は知識の先取りより、豊かな感覚体験と生活のリズムを整えることに価値を置きます。想像力が豊かで創作が好きな子に相性の良いメソッドです。
レッジョ・エミリア|探究プロジェクトとドキュメンテーション
レッジョ・エミリア方式では、子どもを「100のことば(多様な表現)」をもつ探究者と捉え、子どもの興味や関心から主体的な長期プロジェクトを深めていきます。
作品や会話を“見える化”するドキュメンテーションで多様な表現や可能性を認め、家庭や地域とも共有します。好奇心が強く、人と一緒に考えるのが好きな子に向きます。
ハイスコープ(Plan–Do–Review)|実行機能を鍛える学びの循環
ハイスコープ教育の特徴は、子どもが「計画する → 実行する → 振り返る」を毎回の活動で繰り返すことです。
たとえば「今日は積み木でどんな家を作るか考える(計画)→ 実際に作ってみる(実行)→ できたものや工夫を振り返る(レビュー)」という流れです。
このサイクルを重ねることで、子どもは自分で考えて調整する力(自己調整力)や学びを客観的に捉える力(メタ認知)を自然に育みます。
アメリカでの長期研究では、ハイスコープ教育を受けた子どもは、将来の学力や収入、就労の安定性が高く、犯罪率も低いという結果が示されています。
これは「早期の学び方の習慣」が一生の基盤になることを意味しています。
STEAM教育|未来社会に対応する統合型学習
STEAM教育は、科学・技術・工学・芸術・数学を組み合わせ、身近な疑問を探究しながら学ぶ方法です。
たとえば「氷はなぜ溶けるの?」「紙飛行機を遠くに飛ばすには?」といった問いを、実験したり作ったり話し合ったりして解決していきます。
幼児期では、難しい計算や知識ではなく、「つくる・試す・話す」といった遊びを通じて、好奇心と問題解決力を育むことが大切です。
日本でも経産省が「未来の教室」として推進しており、これからますます注目される学び方です。
引用:経済産業省>未来の教室
ピラミッドメソッド|主体性と安心感を両立する設計
ピラミッドメソッドはオランダで生まれた教育法で、大人の支援と子どもの自由のバランスを大切にします。
先生や親が「安心できる環境」と「やる気を引き出すきっかけ」を用意し、子どもはその中で自分の興味をもとに活動を選びます。
たとえば「野菜をテーマにした一週間」では、大人が絵本や実物を準備(支援)し、子どもは「絵を描く」「料理ごっこをする」「育てて観察する」など好きな方法で探究します。
こうして、安心感の中で挑戦し、自主性を育てるのが特徴です。
【日本発祥】独自に発展した幼児教育メソッド
 日本で生まれた幼児教育メソッドは、家庭の生活習慣や学校文化に馴染みやすいのが特長です。
日本で生まれた幼児教育メソッドは、家庭の生活習慣や学校文化に馴染みやすいのが特長です。
ここでは代表的な3つの方法を比較しながら、理念・実践・家庭での取り入れやすさを整理します。
| メソッド | 特徴 | 向いている子ども | ポイント・注意点 |
| 七田式教育 | フラッシュカードで右脳を刺激し全脳活用を促す | 記憶力がよく繰り返しを楽しめる子 | 記憶力・想像力の向上、親子の関わり強化 |
| ヨコミネ式教育法 | 運動・読み書き・計算を段階的に積み上げる | 競争や目標にモチベーションが湧く子 | 自立心・達成感・挑戦意欲の育成 |
| 石井式漢字教育 | 幼児期から漢字に触れて語彙力を伸ばす | 言葉や文字に興味が強い子 | 語彙力・読解力の向上、言語への関心深化 |
七田式教育|右脳刺激と全脳アプローチ
七田式教育は、日本で広まった「右脳刺激」を重視する教育法です。フラッシュカードやリズム遊びを通して、視覚や聴覚に素早い刺激を与え、記憶力や想像力を育てます。
ただし、刺激の量やスピードに頼りすぎると子どもが疲れてしまうため、子どもの反応を見て負荷を調整することが大切です。
無理のない範囲で実践すれば、家庭でも取り入れやすいメソッドです。
ヨコミネ式教育法|目標設定と反復で自立を促す
ヨコミネ式は「できることから少しずつ挑戦し、自立へ導く」ことを重視する教育法です。
運動・読み書き・計算を段階的に積み重ねる仕組みで、目標達成や反復練習から達成感を得やすいのが特徴です。
負けず嫌いで努力型の子どもに相性がよい一方、過度の競争や比較はプレッシャーになりやすいため、指導や家庭での声かけに配慮が必要です。
石井式漢字教育|語彙・表記に早期から触れる
石井式は、幼児期から漢字に触れることで語彙や読解力の基盤を育てる方法です。
絵本や詩に漢字を取り入れることで、子どもは「意味」と「形」を結びつけながら自然に言葉を覚えていきます。
文字や言葉に関心が強い子どもに向いており、生活体験と組み合わせると理解が深まります。
例えば「リンゴ」という文字を学ぶ際に実物を見たり食べたりすることで、記憶が定着しやすくなります。
心理学的観点からの選び方|「子ども×家庭×園・教室」の適合で決める
 「どれが一番よいか」より「うちの子に合うか」です。気質・発達段階・家庭のリソースに合わせて、過不足なく選ぶためのチェックポイントを心理学の視点で示します。
「どれが一番よいか」より「うちの子に合うか」です。気質・発達段階・家庭のリソースに合わせて、過不足なく選ぶためのチェックポイントを心理学の視点で示します。
子どもの気質タイプ別|相性の見きわめ
子どもの気質によって、向いている教育法は大きく異なります。
集中して一人で取り組むのが得意な子もいれば、友達と一緒に探究するのが好きな子、芸術や自然に心を動かされる子、競争で力を発揮する子もいます。
大切なのは「人気だから」ではなく「わが子に合うか」で選ぶことです。
ここでは、代表的な気質タイプごとに相性の良い教育法を一覧にまとめました。
| 子どものタイプ | 相性の良い教育法 |
| 集中して黙々派 | モンテッソーリ/ハイスコープ |
| 好奇心の塊・表現好き | レッジョ・エミリア/STEAM |
| 芸術・自然が好き | シュタイナー |
| 目標で燃えるタイプ | ヨコミネ式 |
同じ園でも“先生×子ども”の相性で体感は変わります。体験時の表情・没頭時間・自発的な発話を観察しましょう。
発達段階別|年齢に応じた選び方
0~2歳は安心できる関係の中で感覚や運動をじっくり育む時期。
3~4歳はごっこ遊びや共同制作を通じて想像力と協調性を伸ばす段階。
5~6歳になると、ルールある遊びや小さなプロジェクトを通じて「計画→実行→振り返り」の流れを学ぶ時期です。
発達に合った刺激を与えることが“ちょうど良い挑戦”につながり、全年齢でサーブ&リターンのやりとりが効果を高めます。
家庭環境別|ライフスタイル適合で無理なく続ける
教育は「家庭に合うかどうか」で成果が変わります。たとえば、平日はオンライン教材や通信教育で基礎を積み、休日には教室や体験活動を厚くする組み合わせも有効です。
通園距離や送迎の負担、兄弟の有無、親の勤務形態などを考慮し、無理なく続けられるスタイルを選ぶことがポイントです。
続けやすい仕組みこそ、最大の費用対効果を生み出す秘訣です。
実践方法と費用比較|失敗しない教育投資の考え方
 教室通いと家庭学習、そして両者のハイブリッド。見落としがちな時間コストや継続性まで含め、費用対効果を最大化する現実的な設計を解説します。
教室通いと家庭学習、そして両者のハイブリッド。見落としがちな時間コストや継続性まで含め、費用対効果を最大化する現実的な設計を解説します。
教室通い vs 家庭学習
一般的に、幼児教室の月謝は1〜3万円程度、習い事や通信教育は3千〜8千円程度が相場です。
送迎や教材費を含めると「1時間あたりの実質コスト」は大きく変わるため、単純な金額比較ではなく「継続可能性」と「子どもの反応」で判断するのが賢明です。
教室通いは、社会性や対話・協働の機会が得られる一方で、送迎の負担や費用の高さがデメリットになります。
対して家庭学習は、自由度と継続性に優れるものの、学習環境の整備や親の関わり方が成果を左右します。
理想は“ハイブリッド”です。家庭ではサーブ&リターンを意識した日常的な関わりを大切にし、教室では他者と協働する体験を積むことで、双方の強みを活かせます。
費用対効果を最大化する賢い選択術
費用対効果を見極めるには、金額の多寡だけでは不十分です。大切なのは、子どもがどれだけ意欲的に取り組めているか、家庭に無理なく続けられているかを定期的に確認すること。
その方法として、毎週「子どもの参加意欲」「家庭での自発的な再現」「保護者の負担感」などを短く記録し、月ごとに振り返りを行うと、投資が成果につながっているかが見えてきます。
また、「年齢に合っているか」「主体性が育っているか」「振り返りが組み込まれているか」という3条件がそろうほど効果は高まると研究でも指摘されています。
OECDも、規則や制度よりも日々の相互作用や振り返りの質こそが教育の成果を左右すると強調しています。
よくある悩みと心理的解決法|専門家が答えるQ&A
 「効果が見えない」「比較してつらい」「教材選びが不安」—よくある悩みはパターン化できます。認知行動のコツと具体策で、迷いを行動に変えましょう。
「効果が見えない」「比較してつらい」「教材選びが不安」—よくある悩みはパターン化できます。認知行動のコツと具体策で、迷いを行動に変えましょう。
Q1.「効果が見えない」―どう判断する?
幼児教育は“後から効く力”が中心です。短期の点数より、①集中が続く時間、②最後までやり切る頻度、③友だちとの関わり、④家での自発再現を指標にしてください。
月1回、親子で写真と一言コメントで振り返ると、微細な成長が見えてきます。
Q2.「他の子と比べて不安」―どう向き合う?
比べる相手は“クラスの誰か”ではなく“過去のわが子”です。3か月前の記録と比べて「できるようになったこと」を確認しましょう。
学びの土台は関係性と環境です。サーブ&リターンの質を上げる方が近道です。
Q3.「教材選びで失敗したくない」―何を見ればいい?
教材を選ぶ際は、まず年齢に合っているか、子どもが自分で選んで取り組める余地があるか、そして学んだことを振り返れる仕組みがあるかを確認しましょう。
体験版があれば実際に試し、子どもが“自分なりのやり方に工夫して継続できるか”を観察するのがポイントです。
親のサポートが少なくても進められる設計であれば、無理なく長続きします。
早期教育の“注意点”も知っておく
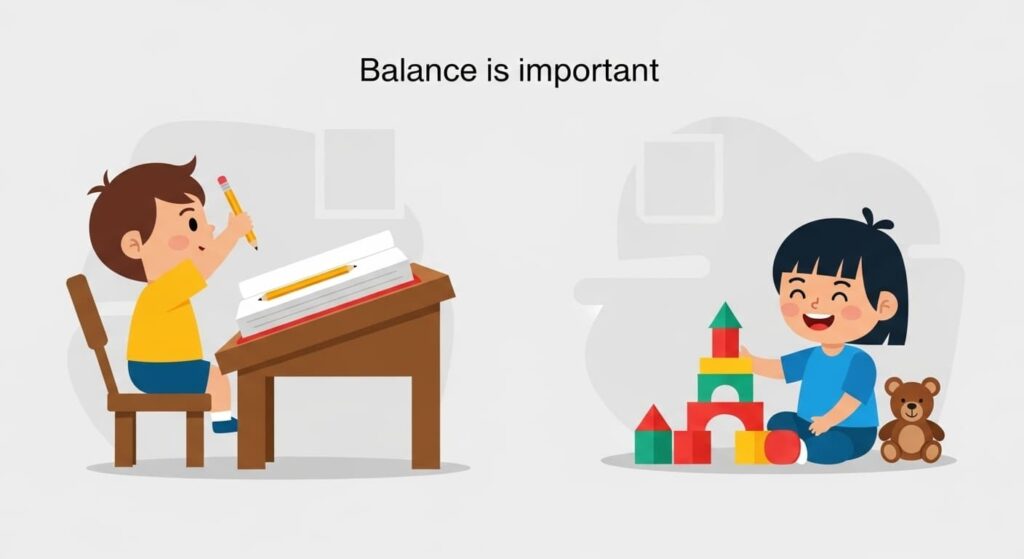 先取り教育では、小さいうちにテストの点数が伸びても、学年が上がるにつれて差が縮んだり相殺されたりするケースがあります。
先取り教育では、小さいうちにテストの点数が伸びても、学年が上がるにつれて差が縮んだり相殺されたりするケースがあります。
これは「先取りに偏りすぎること」「教育の質が不十分なこと」「小学校以降との接続が途切れること」が原因であり、幼児教育そのものを否定するものではありません。
K-3の学びをつなぐ具体的な実践
「K-3をつなぐ」とは、単にカリキュラムを並べるのではなく、年齢に応じた相互作用と振り返りを少しずつ高度化していくことが、子どもの学びを持続的に伸ばすポイントです。
| 年齢・学年 | 相互作用(関わり方) | 振り返り(リフレクション) | 活動例 |
| 就学前
(3〜5歳) |
サーブ&リターンを意識した応答(子どもの声かけに即反応) | 「今日楽しかったことは?」「どんな工夫をした?」と簡単に言葉にする | ・ごっこ遊び
・製作活動 ・自然観察 ・絵本を題材にした会話 |
| 小学1〜2年
(6〜7歳) |
グループ活動やペアワークで意見交換の機会を増やす | 授業後に「できたこと・できなかったこと」を絵や日記で表現 | ・生活科の観察記録
・工作の発表 ・簡単な実験と振り返り |
| 小学3年
(8〜9歳) |
教師が問いかけで思考を深める(答えを与えすぎない) | 「どうすればもっとよくできる?」を友達同士で話し合う/自己評価表 | ・地域調べ学習
・小さなプロジェクト学習 ・発表と改善活動 |
就学前(3〜5歳/幼稚園・保育園期)は、先生や親とのやり取りで「サーブ&リターン」を意識し、子どもの発話や行動にすぐ応答することが大切です。
遊びや生活の中で「今日楽しかったことは?」「どんな工夫をした?」と簡単に言葉にさせることで、感情や経験を言語化する練習となり、言語能力の発達にもつながります。
ごっこ遊びや製作活動、自然観察を通じて、思考や気持ちをのびのびと表現できる環境を整えましょう。
小学1〜2年生(6〜7歳)になると、自分の考えを他者に伝える力が重要になります。
授業や遊びの中でグループ活動やペアワークを取り入れ、友達と意見を交換する機会を増やすことが効果的です。
学びを振り返る際には「できたこと」「できなかったこと」を絵や日記にまとめ、成果と課題を自分の言葉で確認する習慣をつけていきます。
生活科や工作の授業などを活用し、「計画→実行→発表→振り返り」の小さなサイクルを繰り返すことで、学びを定着させることができます。
小学3年生(8〜9歳)になると、より論理的な思考や自己評価の力を育てる段階に入ります。
教師は答えを与えるのではなく、問いかけや対話を通じて「なぜ?」と考えさせることで、子どもの探究心を深めます。
振り返りの場面では、友達同士で「どうすればもっとよくできるか」を話し合い、簡単な自己評価表を使って自分の学びを見直します。
地域の調べ学習のような短いプロジェクトに取り組み、情報を集め、まとめ、発表し、その後改善点を見出す経験を重ねることで、計画性や協働性も高まります。
こうして就学前は感情や経験を言葉にして振り返る練習を、小学低学年では小さな学びのサイクルを習慣化し、小学3年生では自己評価や仲間とのフィードバックを取り入れる学びへと発展させていきます。
つまり「K-3をつなぐ」とは、単にカリキュラムを並べるのではなく、年齢に応じて相互作用と振り返りを少しずつ高度化させ、学びの土台を持続的に積み上げていくことなのです。
家庭と学校の連携で支える学び
 子どもの学びを持続的に伸ばすには、家庭と学校・園がそれぞれの強みを活かして補い合うことが欠かせません。
子どもの学びを持続的に伸ばすには、家庭と学校・園がそれぞれの強みを活かして補い合うことが欠かせません。
家庭では安心感と日常体験を通じた学びを、学校や園では仲間との協働や探究的な体験を重ねることで、子どもは安定と挑戦の両方を経験できます。
ここでは、就学前から小学校3年生までの時期に、親と先生が実践できる具体的な工夫を整理しました。
K-3の学びを支える家庭と学校の連携
K-3期(就学前から小学3年まで)は、学びの連続性を意識して「家庭での関わり」と「学校・園での実践」をつなぐことが大切です。
家庭では安心感と日常体験を通じた学びを、学校や園では集団活動やプロジェクトを通じた社会的な学びを補い合うことで、子どもは安定と挑戦の両方を経験できます。
ここでは年齢ごとに、家庭と学校それぞれで実践できる工夫を整理しました。
| 年齢・学年 | 家庭でできる工夫(親向け) | 学校・園での実践(先生向け) |
| 就学前
(3〜5歳) |
絵本を読んだ後に「どんな気持ちになった?」と問いかける/一緒に工作や料理をして「やってみたい」を尊重 | サーブ&リターンを意識し、子どもの発話や仕草に即応答/ごっこ遊びや製作活動を通じて協働体験を促す |
| 小学1〜2年
(6〜7歳) |
学校で学んだことを家庭で「今日は何をしたの?」と振り返る習慣をつける/観察日記を一緒に記録 | グループ活動やペアワークで意見交換を経験させる/授業後に日記や絵で「できたこと・工夫したこと」を振り返らせる |
| 小学3年
(8〜9歳) |
家庭で調べ学習をサポートし、発表の場を作る(家族へのプレゼンなど)/子ども自身に「次はどうする?」と問いかける | 教師が問いを投げかけて子どもの思考を深める/簡単な自己評価表や友達同士のフィードバックを取り入れる |
このように、家庭と学校・園が役割を分担しながら学びを支えることで、子どもは段階に応じて「安心→挑戦→振り返り」と成長を積み重ねていけます。
大切なのは、どちらか一方に偏るのではなく、両者が補完し合う関係を築くことです。
家庭で芽生えた興味が学校で深まり、学校で得た経験が家庭で振り返られることで、学びはより豊かに広がります。
関連コラム
本記事の理解をさらに深めていただくために、幼児教育メソッドの比較、年齢別の実践法、家庭で続ける仕組みづくりを扱った関連記事を3本まとめました。
子育てに役立つチェックポイントや費用対効果の見方も整理できます。明日からの取り組みに直結する内容ですので、ぜひあわせてご覧ください。
● 【心理学で解明】幼児教育は本当に意味ない?研究データから見る効果と正しい選び方
● 幼児教育とは?心理学と脳科学で読み解く始め方・効果・実践法を解説
● 家庭でできる幼児教育の【完全ガイド】共働きでも続く学びの習慣と教材選び
おすすめ書籍
モンテッソーリ教育・レッジョ・エミリア教育を知り尽くした オックスフォード児童発達学博士が語る 自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方 3歳 〜 12歳 の子ども対象
「モンテッソーリ教育」と「レッジョ・エミリア」の要点を、オックスフォードで児童発達を研究した著者がやさしく解説しています。
主体性を育てる環境づくりや“ほめ方・声かけ”、家庭での実践例まで、各メソッドの違いと共通点が整理でき、忙しい共働き家庭でも始めやすい入門書です。
まとめ
今回の記事では、幼児教育メソッドの選び方を、心理学と最新のエビデンスに基づいて紹介しました。
● 主要メソッドの特徴と向き不向き
● 年齢・気質・家庭環境に合う選定基準
● 費用対効果を高める実践(PDCAとハイブリッド)
まずは気になるメソッドを1つ選び、小さく試してみましょう。体験教室や通信教材の無料体験を活用し、子どもの反応を観察することが第一歩です。
大切なのは「完璧な方法を探す」より「家庭に合う方法を柔軟に調整する」姿勢です。
出典リンク
● 文部科学省>幼児期の終わりまでに育ってほしい姿
● OECD>Starting Strong Ⅵ(EN)
● HighScope財団「ペリー就学前教育計画(長期追跡の主要結果)」
● Heckman Equation(就学前教育の投資収益率の推計)
● Harvard Center on the Developing Child(サーブ&リターン/実行機能)
● Tennessee州プリK長期評価(質・接続が不十分だと効果が薄れる可能性)
● 経済産業省「未来の教室」(STEAM推進の政策動向)



