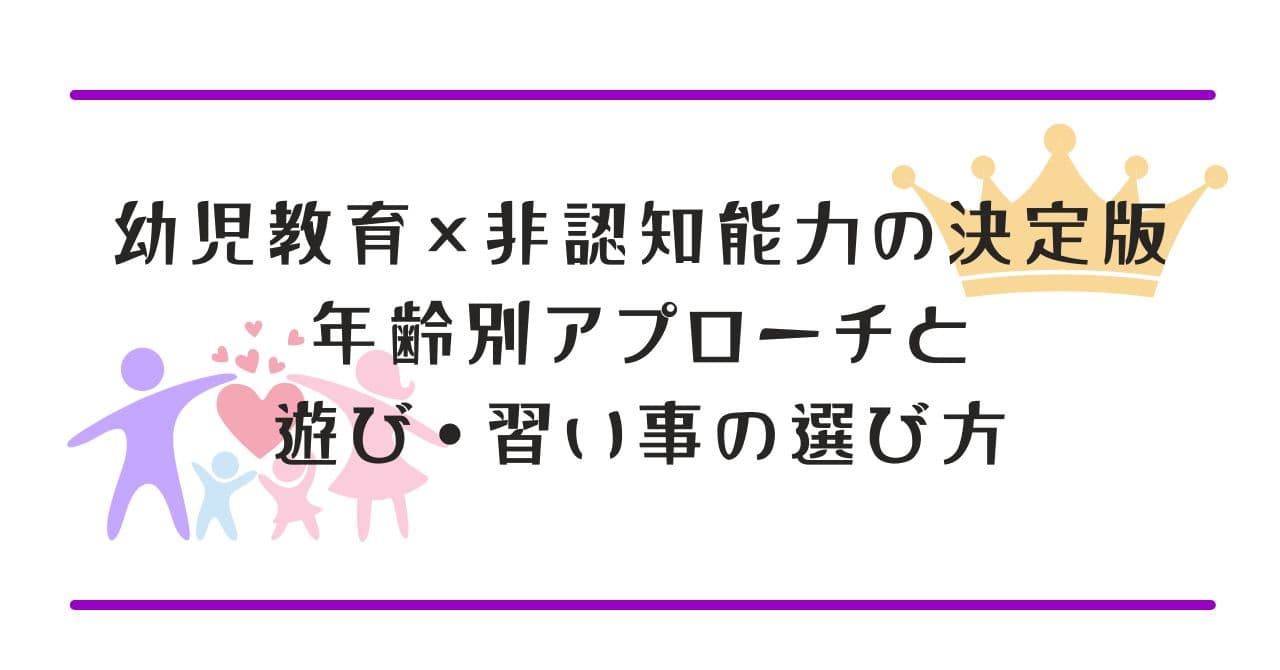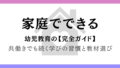これからの時代、本当に必要な力って何だろう?」
テストの点数だけでは測れない“ある能力”が、今、世界中で注目されています。
それは、子どもの将来の学力だけでなく、人生そのものに深く関わる力。
ですが、その正体や育て方は、まだあまり知られていません。
この記事では、幼児教育の中で“その力”をどう育てていけるのかを、年齢別・家庭別に具体的にご紹介します。
「今すぐ始められるヒント」も交えながら、未来に必要な“見えない力”の本質に迫ります。
幼児教育で注目される「非認知能力」とは?IQでは測れない“生きる力”
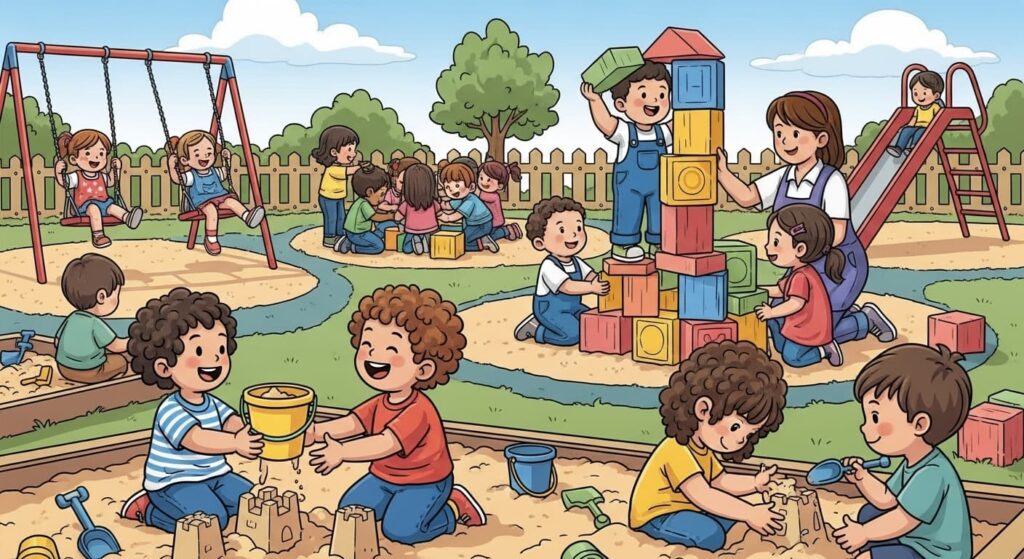
近年の幼児教育では、テストでは測れない「非認知能力」が重視されています。
感情を調整したり、最後までやり遂げたり、人と協力できる力は、IQとは異なる“生き抜く力”です。
この力は、幼児期にこそ育ちやすく、大人になってからの学力や幸福度にも大きく影響するといわれています。
認知能力と非認知能力の違いをわかりやすく解説
・認知能力=言語・計算・記憶・論理など“数値で測れる知能”
・非認知能力=やる気・共感力・自己肯定感など“数値では測れない心の力”
認知能力はIQやテストで評価される一方、非認知能力は性格や態度、意志の強さなどに関わります。たとえば「最後までやり抜く力」や「友達と仲良くする力」は非認知的な側面です。
幼児期はこの非認知能力の土台を築く最重要期であり、早期に育てることで、後の学習態度や社会性にもよい影響を与えます。
非認知能力の主な種類(意欲・自己肯定感・共感性など)
非認知能力には、次のような多面的な力が含まれます。
・自己肯定感(自分を信じる力)
・共感性(他人の気持ちを理解しようとする力)
・自己制御(感情を落ち着かせる力)
・やり抜く力(困難に向き合う粘り強さ)
・自己効力感(「自分ならできる」という感覚)
・社会的スキル(協力・役割意識など)
これらは遊び・生活・対人関係の中で自然に育ちます。
幼児教育では、意識的な関わりによって、こうした力を日々の中で伸ばしていくことが重要です。
| 能力の種類 | 特徴(どんな力?) | 育ちやすい場面例 |
|---|---|---|
| 自己肯定感 | 自分に価値があると感じられる力 | 大人に受け入れられ、共感される経験 |
| 共感性 | 他人の気持ちを理解しようとする力 | ごっこ遊びや友達との対話の中 |
| 自己制御 | 感情や衝動をコントロールする力 | 順番を待つ遊び・ルールのある活動 |
| やり抜く力 | 途中で諦めず最後まで取り組む力 | 難しい課題・繰り返し挑戦できる遊び |
| 自己効力感 | 「自分ならできる」と思える感覚 | 成功体験の積み重ね・励ましの声かけ |
| 社会的スキル | 協力・責任感・役割意識など対人関係の力 | 共同制作・役割分担のあるグループ活動 |
なぜ今「非認知能力」が世界中で注目されているのか?
非認知能力は「幸せに生きる力」として、世界的に教育の中心に据えられつつあります。
経済学者ヘックマン博士の研究では、非認知能力が将来の収入や雇用・健康・犯罪率にまで影響すると判明。
OECDのPISA調査でも、回復力や協調性が学力以上に重要な指標とされています。
これを受け、各国の幼児教育ではIQ偏重から“心の教育”へと舵を切っています。
日本でも文部科学省が「非認知能力の育成」を重要視し、保育指針にも明記しています。
こうした背景から、非認知能力は“今の子どもたち”に必要不可欠な力とされています。
幼児教育が子どもの非認知能力に与える影響とは?

幼児教育を通じて育まれる非認知能力は、単なる性格形成に止まらず、学力や将来の職業選択、さらには年収や社会適応力にも大きく関わります。
本パートでは、具体的な研究成果やエビデンスをもとに、幼児期の教育がどのように子どもたちの非認知能力を形成し、人生の長期成果に影響するのかを科学的に掘り下げます。
非認知能力は学力・年収・就職にも影響するって本当?
非認知能力が高い子どもは、いわゆる“社会情緒的スキル”に優れており、学習への前向きな姿勢や人間関係の安定に強みを持つとされています。
文部科学省やJ-STAGEに掲載された研究によると、「学習意欲が高い子どもほど、教科の正答率も高くなる」という傾向が確認されています。
また、幼児期に非認知スキルを育てる教育を受けた子どもは、将来の就職率や年収面でも有利であるという報告もあります。
さらに、AIや自動化が進む現代社会では、以下のような力が“社会人基礎力”としてますます重視されています。
・協調性やチームでの対応力
・柔軟な思考・創造力
・自分を律する自己管理能力
つまり、非認知能力は「テストでは測れないが、人生を左右する力」として、幼児教育の中でも極めて重要な柱になりつつあるのです。
40歳時点の差を生んだ幼児教育の研究【経済学的エビデンス】
アメリカの長期研究「ペリー就学前プロジェクト(Perry Preschool Project)」では、質の高い幼児教育を受けた子どもと、受けなかった子どもの40歳時点の差が検証されました。
結果は明確で、幼児教育を受けたグループは以下の点で有意な差が見られました。
・高卒率・大卒率の上昇
・年収・雇用安定性の向上
・犯罪率・生活保護依存率の低下
特筆すべきは、「IQの上昇」よりも「非認知能力の向上」が長期成果に影響していた点です。
これにより、経済学の分野でも「教育への早期投資は極めて高いリターンを生む」との評価が確立しました。
自己決定や感情コントロール力が人生を豊かにする理由
非認知能力の中でも、「自己決定力」や「感情のコントロール力」は、人生の質や幸福感を大きく左右すると多くの研究で示されています。
自分で選び、自分で判断し、その結果に責任を持つ経験が多い子ほど、主体性・問題解決力・内発的動機が育まれることが分かっています。
また、感情をうまく調整できる子どもは、人間関係でのトラブルが少なく、学びや遊びに集中しやすくなる傾向があります。
これは将来の職場・家庭生活でも重要な基盤です。
こうした力は、幼児期の遊びや日常生活の中で自然に育まれていくのです。
| 自己決定力・感情コントロール力が及ぼす影響(比較表) | ||
| 項目 | 高い場合に見られる傾向 | 低い場合に見られる傾向 |
| 自己決定力 | 自信・責任感・内発的動機の向上 | 他人任せ・不安感・学習意欲の低下 |
| 感情コントロール力 | 集中力・人間関係スキル・トラブル回避能力の向上 | 癇癪・衝動行動・対人トラブルが増える |
| 将来的な影響(職業・生活) | 職場での安定性・自己管理能力・ストレス耐性が高い | 離職・対人ストレス・環境適応の難しさ |
| 教育効果 | 長期的な学習意欲と習熟度の向上 | 学習継続の困難・集中力の欠如 |
幼児教育における非認知能力の年齢別アプローチ【0〜6歳】

非認知能力は、一度にまとめて育てられるものではなく、年齢に応じたアプローチが重要です。
幼児期は心の発達が著しい時期であり、成長段階に合わせた関わり方が、能力の土台を形成します。
以下では、0〜6歳までの年齢別にどのような非認知能力を意識し、どんな環境や関わりが効果的かを具体的に紹介します。
0〜2歳|安心感と親子の信頼関係が土台をつくる
乳幼児期は、非認知能力の“根っこ”となる情緒の安定と基本的信頼感を育む時期です。
この時期の子どもは、言葉よりもスキンシップや表情から安心感を得ています。
親や保育者との愛着形成がうまくいくことで、「自分は大切にされている」と感じる自己肯定感の基礎が築かれます。
泣いたときに応えてもらえる、遊びに寄り添ってもらえる――こうした日々の繰り返しが、やがて感情の安定や自己制御力の土台となります。
0〜2歳は「非認知能力を育てる準備期」として、まず“心の安全基地”をつくることが最優先です。
3〜4歳|遊びとお手伝いで自己肯定感と粘り強さを育む
この時期の子どもは、自分でやってみたいという欲求が高まり、「できた!」という体験を積み重ねたがります。
非認知能力の中でも、自己肯定感や粘り強さ、挑戦への意欲が育ちやすい時期です。
たとえば、簡単なお手伝いや工作遊びに取り組ませ、成功体験を言葉でしっかり認めることが大切です。
失敗したときも、「いいチャレンジだったね」「またやってみよう」と前向きに声かけすることで、「うまくいかなくても大丈夫」という心理的安全が育ちます。
ごっこ遊びや協同作業を通じて、他者とのやりとりの楽しさや我慢する力も学べます。
この時期は“挑戦と承認”の積み重ねで、非認知能力が一気に伸びるタイミングです。
5〜6歳|友達との関わりで協調性・社会性を学ぶ
集団での活動が本格化する5〜6歳は、非認知能力の中でも「協調性」や「社会的責任感」が大きく育つ時期です。
友達と協力して何かを作る、ルールのある遊びに参加する、意見がぶつかっても解決を試みる――そうした日々のやりとりの中で、自分の感情を調整したり、他人の気持ちを想像する力が伸びていきます。
とくにこの時期は「どうやったらうまくいくか?」を考える自己調整力が芽生え、将来の“話し合い力”や“思いやり”の基盤となる力が自然と育まれていきます。
家庭では、「友達との出来事」をじっくり聞いてあげる時間が、信頼と社会性の育成につながります。
非認知能力の“実践期”ともいえるこの段階では、集団の中での経験が何よりの教材です。
家庭でできる幼児教育|非認知能力を育てる関わり方

非認知能力は、特別な教育プログラムや教材がなくても、家庭の中で自然に育てていくことができます。
毎日の声かけや接し方が、子どもの心に安心感と挑戦心を育て、やがて自己肯定感や社会性に結びついていきます。
ここでは、家庭で今日から実践できる“非認知能力を育てる関わり方”の基本を紹介します。
子どもの意思決定を尊重することの大切さ
子どもが「自分で決める」経験を重ねることは、非認知能力の中でも特に重要な“自己決定力”を育てます。
たとえば、洋服を選ぶ・遊びの順番を決める・おやつを選ぶなど、小さな選択でもOKです。
「自分の考えを尊重される体験」は、自己肯定感や責任感の基盤となります。
親がなんでも先回りして決めてしまうと、子どもの内発的動機が育ちにくくなるため要注意です。
大切なのは、選択肢を与えながら“自分で決めた”という感覚を育むこと。
間違いや後悔も含めて経験と捉えることで、子どもの主体性はぐんと伸びていきます。
「失敗してもいいよ」と伝えることで生まれる挑戦力
非認知能力のひとつ「やり抜く力(GRIT)」は、失敗を恐れず挑戦できる環境で育まれます。
家庭では、失敗したときに怒ったり責めたりするのではなく、「失敗しても大丈夫」「やってみたことがすごい」と伝えることが大切です。
この“心理的安全性”が確保されると、子どもは新しいことにも積極的に取り組むようになります。
チャレンジの結果よりも「挑戦した勇気」や「工夫した過程」に目を向けて声をかけることで、「自分にはできる」という自己効力感も育ちます。
失敗を恐れない姿勢は、将来の学び・仕事・人間関係すべてに役立つ力となります。
「過程を褒める」声かけがやる気を引き出す
子どものやる気を引き出すには、「結果」ではなく「過程」に注目して褒めることが効果的です。
たとえば「100点とって偉いね」ではなく、「毎日コツコツ頑張ってたね」のような声かけが◎。
努力や工夫に目を向けることで、子どもは“自分の頑張りが認められた”と感じ、内発的な動機づけにつながります。
また、過程を褒めることで「できないことがあっても挑戦していい」という安心感も育ちます。
この関わり方は、学力だけでなく、非認知能力全般(意欲・自己制御・粘り強さなど)を伸ばす土壌となります。
「できた/できない」で判断せず、「取り組んだ姿勢」に注目することで、子どもは自信を深めていきます。
非認知能力を伸ばす幼児教育の遊び・教材・習い事とは?

非認知能力は、生活の中での体験を通じて自然に育ちます。
特に「遊び」は、子どもにとって最高の学びの場。
さらに、適切な教材や習い事の選択が、非認知能力をより深く育てる手助けになります。
ここでは、日常の遊びや教育法、教材の選び方を通じて、どのように“心の力”を伸ばすかを解説します。
のりもの遊びやごっこ遊びが育てる想像力と協調性
のりものやごっこ遊びには、非認知能力を育てる要素がたくさん詰まっています。
たとえば電車や車のおもちゃで遊ぶことで、子どもは想像の世界を広げながら、順番を待つ・ルールを守るといった社会性も学びます。
ごっこ遊びでは、店員さん・お客さん・お医者さんなどの役割を演じることで、他者の視点に立つ「共感力」が養われます。
・想像力
・協調性
・感情の表現力
・ルール理解と自己制御力遊びながら学ぶことで、子ども自身が「楽しい」と感じながら、内面の力を自然に伸ばしていくのがポイントです。
モンテッソーリ・レッジョ・EQ教育など非認知型プログラムの特徴
非認知能力の育成を重視した教育法には、以下のようなものがあります。
・モンテッソーリ教育
→ 自由選択・自己決定を尊重し、集中力と責任感を育てる
・レッジョ・エミリア教育
→ アートや対話を重視し、自己表現・共感性を育む
・EQ教育(情動知能教育)
→ 感情理解や他者との関係づくりを中心に据えた心の教育
これらのプログラムは、知識や記憶ではなく「人としてどう育つか」に焦点を当てており、近年では日本の幼児教室や保育園にも一部取り入れられています。
共通するのは、子どもが自ら考え、選び、体験するプロセスを大切にしている点です。
通信教育・市販教材で選ぶなら?非認知能力に強い教材の見分け方
市販の知育教材や通信教育でも、非認知能力を意識した商品が増えています。
選ぶ際は「知識の詰め込み型」ではなく、考える過程ややり取りを重視する教材を選ぶことがポイントです。
市販の知育教材や通信教育を選ぶ際には、以下のポイントを確認してみましょう。
「考える力」や「感情を育む力」を伸ばす教材かどうか、見極めのヒントになります。
□ ステップアップ形式ではなく、自由に取り組める構造になっている
□ 保護者との会話や関わりを促す設計がある
□ 子どもが自分のペースで成功体験を積み重ねやすい仕組みがある
たとえば、「失敗してもOK」「自分なりの正解を見つけよう」といった声かけが促されるワークブックや、親子のやりとりを楽しめるアプリ教材などは非認知能力の育成に効果的です。
共働き家庭でもできる幼児教育|非認知能力を育てる工夫

忙しい日々の中でも、子どもの「心の力=非認知能力」を育てることは可能です。
大切なのは“長時間向き合うこと”より、“日常に心を込めること”。
ここでは、共働き家庭でも無理なく取り入れられる工夫と、教育環境の選び方をご紹介します。
忙しくても実践できる“ながら関わり”の工夫
共働き家庭にとって、時間の制約は避けられない現実です。
でも「ながら関わり」を意識するだけで、日常が立派な幼児教育の場になります。
具体例
・朝の着替え中に「今日は何をしたい?」と問いかける
・夕食の準備中に「今日の楽しかったこと」を聞いてみる
・一緒に洗濯物をたたみながら、「ありがとう」と感謝を伝える
こうした短時間の関わりでも、子どもは「自分に関心を持ってもらえている」と感じ、自己肯定感や感情表現力といった非認知能力が育まれます。
“ながら”でも「心を向ける時間」に変えることで、確かな効果が生まれます。
保育園・幼稚園選びでチェックしたいポイントとは?
子どもが安心して通える園は、非認知能力を育む土台になります。
以下のポイントを見学時にサッとチェックしてみましょう。
□ 自由に遊ぶ時間がしっかりある
□ 子どもの発言に先生がきちんと耳を傾けている
□ 子どもの個性やペースを大切にしている
□ 友達同士で関わる活動が多い
□ 感情を言葉にできるような声かけがある
□ 先生たちの雰囲気が明るく穏やか
□ 子どもたちが楽しそうに過ごしている
カリキュラムよりも、子どもと先生の関係性や園全体の雰囲気をよく観察すること。
「ここなら安心して通わせられる」と思える空気感が、なによりの判断基準です。
家族で協力して育てる「心の力」
非認知能力は、母親や父親だけでなく、家庭全体で育む力です。
祖父母や兄弟との関わり、パートナーとの協力体制があるだけで、子どもは多様な関わり方を経験し、共感力や社会性を身につけていきます。
家庭でできる協力の工夫
・朝や夜の短い時間に「今日のありがとう」を伝え合う
・パートナー同士で子どもの成長を共有・ねぎらう
・おじいちゃん・おばあちゃんとも“ありがとう”のやりとりを
1人で頑張りすぎず、“家族みんなで育てる”という意識を持つことが、子どもにとっても「人と関わる心地よさ」を学ぶ、最高の教材になります。
幼児教育に関する非認知能力のよくある質問【Q&A】

非認知能力は「見えにくい」「測りにくい」力だからこそ、親としては「本当に育っているの?」「やり方は合ってる?」と不安になることもあります。
ここでは、保護者からよく聞かれる疑問に対して、わかりやすくお答えします。
Q1. 非認知能力はどうやって評価できる?数値化できますか?
・自分から挑戦しようとする
・困っている子に声をかける
・我慢したり気持ちを切り替えられる
・最後まで取り組もうとする姿勢がある
また、保育園や一部の教育機関では、非認知能力のチェックシートや観察記録を活用し、子どもの成長を見守る仕組みも整ってきています。
Q2. 放任でも育つもの?逆に手をかけすぎるとダメ?
大切なのは「干渉せずに、見守る」関わり方です。
・子どもの代わりに判断する
・失敗を厳しく叱る
・失敗も一緒に振り返る
・小さな努力に気づいて褒める
“やりすぎず、見過ごさず”のちょうどよい距離感が、心の育ちを支えます。
Q3. 認知能力と非認知能力、どちらを優先すべき?
ただし、非認知能力は認知能力を支える土台になります。
たとえば
・「集中力」や「粘り強さ」があってこそ学習が続きます。
・「自信」や「好奇心」が新しいことを学ぶ意欲を育てます。
・「感情のコントロール」が学びや人間関係の安定に役立ちます。
先に“心の力”が育つことで、その後の「学力の伸び」も自然とついてくるのです。
研究と現場から学ぶ幼児教育と非認知能力の育て方

非認知能力の重要性は、国内外の教育研究だけでなく、実際の保育現場でも広く認識されつつあります。
最新の調査や実践事例からは、どのような環境・声かけ・関わりが「心の力」を育てるのか、具体的な知見が得られています。
ここでは、東京大学の研究をはじめ、保育士や幼児教室の現場の取り組みを紹介し、家庭で活かせるヒントも探っていきます。
東京大学Cedepの調査に見る効果と取り組み事例
東京大学の発達保育実践政策学センター(Cedep)は、非認知能力に関する大規模な調査研究を実施しています。
令和3年度の文部科学省委託事業では、保育施設における非認知能力の育成実践を検証。
調査では、子どもの「主体性」「共感性」「感情調整力」が、園の取り組みや保育者の関わりによって着実に育まれていることが示されました。
・子どもが活動内容を選べる「選択保育」
・友達と対話しながら進める「協同的な遊び」
・保育士の共感的な声かけ(例:「そうだったんだね」)
これらの要素が、子ども自身の“気持ちの自覚”や“他者理解”を高める効果をもつと報告されています。
現場の保育士・幼児教室が実践する指導ポイント
多くの現場では、非認知能力を育てる保育の実践が行われています。
中でも重視されているのが、「遊び」と「関わり」の質です。
現場で実践されている主な工夫
・子どもの選択を尊重し、やりたい遊びを自分で決めさせる
・失敗や感情のゆれに対して、共感しながら寄り添う
・活動の過程を丁寧に認め、努力を言語化して伝える
幼児教室でも、「自分で気づき、考え、工夫する力」を伸ばす教材やプログラムが取り入れられています。
先生の接し方一つで、子どもの意欲・社会性は大きく変化すると現場でも実感されています。
家庭と園の連携がカギを握る理由
非認知能力の育成は、園だけで完結するものではありません。
家庭と保育・教育現場が一体となって“心の成長”を見守ることが不可欠です。
子どもは、家庭と園での関わり方に「一貫性」があると安心感を得やすく、
自分の感情や行動に自信を持ちやすくなります。
・園での様子を家庭で共有し、家庭でも同様の声かけを意識する
・保護者が保育士と情報交換しやすい関係を築く
・子どもの感情や行動の変化について、お互いにフィードバックする
「家での関わり」「園での経験」がつながっていると感じることで、子ども自身も“心の育ち”をより確かにしていきます。
関連コラム

非認知能力や幼児教育に関する理解をさらに深めたい方に向けて、関連するコラムをいくつかご紹介します。
北欧の教育文化、日本の実践事例、遊びや心理学的観点からのアプローチなど、どれも家庭での実践に役立つ内容です。
気になるテーマがあれば、ぜひあわせてご覧ください。
世界一幸せな国・デンマークの幼児教育とは?日本との違いと家庭での実践ヒント
デンマークでは子どもを「市民」として尊重し、自由と信頼に満ちた環境で育てる文化があります。遊びを通じた学び・自己肯定感の促進・自然と対話する保育など、非認知能力の基盤となる価値観が随所に散りばめられています。
日本の子育てにも応用できる具体的なアプローチが豊富に紹介されています。
幼児教育における「遊び」の重要性とは?年齢別・発達段階別の選び方から実践方法まで
「遊び=学び」という北欧由来の哲学を背景に、発達段階に応じた遊び方の工夫を解説しています。
想像力・協調性・感情表現など、非認知能力を自然に育みやすい環境づくりについて具体的な事例とともに紹介。
家庭でも取り入れやすいアイデアが満載です。
幼児教育とは?心理学と脳科学で読み解く始め方・効果・実践法を解説
心理学・脳科学の視点から、0〜6歳の子どもの「育つ力」を引き出す関わりと環境構成について体系的にまとめられています。
非認知能力だけでなく、認知能力や人間関係力との関連も詳しく解説。
家庭や教育現場での実践ヒントが豊富で、エビデンスを伴う信頼性の高い内容です。
おすすめ書籍|『非認知能力の育て方 心の強い幸せな子になる0〜10歳の家庭教育』
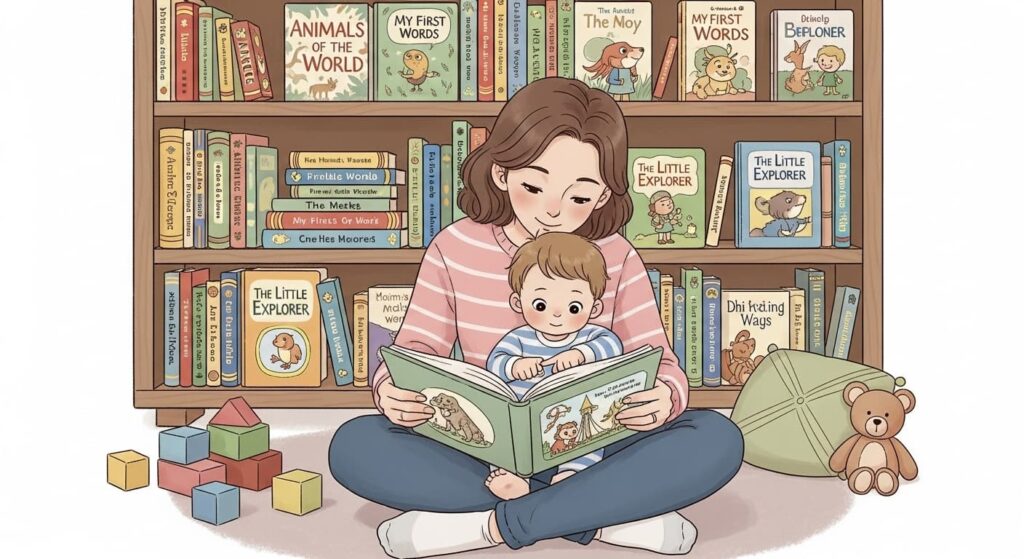
家庭で非認知能力を育てたい方に向けた、分かりやすく実践的な一冊です。
著者はボーク重子さん。
娘さんを「全米最優秀女子高生」に育てた子育て体験にもとづき、「共感」「挑戦」「自己肯定感」などを自然に伸ばす家庭教育のコツを具体的に提示しています。
図解やQ&A、事例も豊富で、教育熱心なご家庭や保育現場の方にもおすすめです。
(Amazonで広くレビューされ、高評価のロングセラーです)