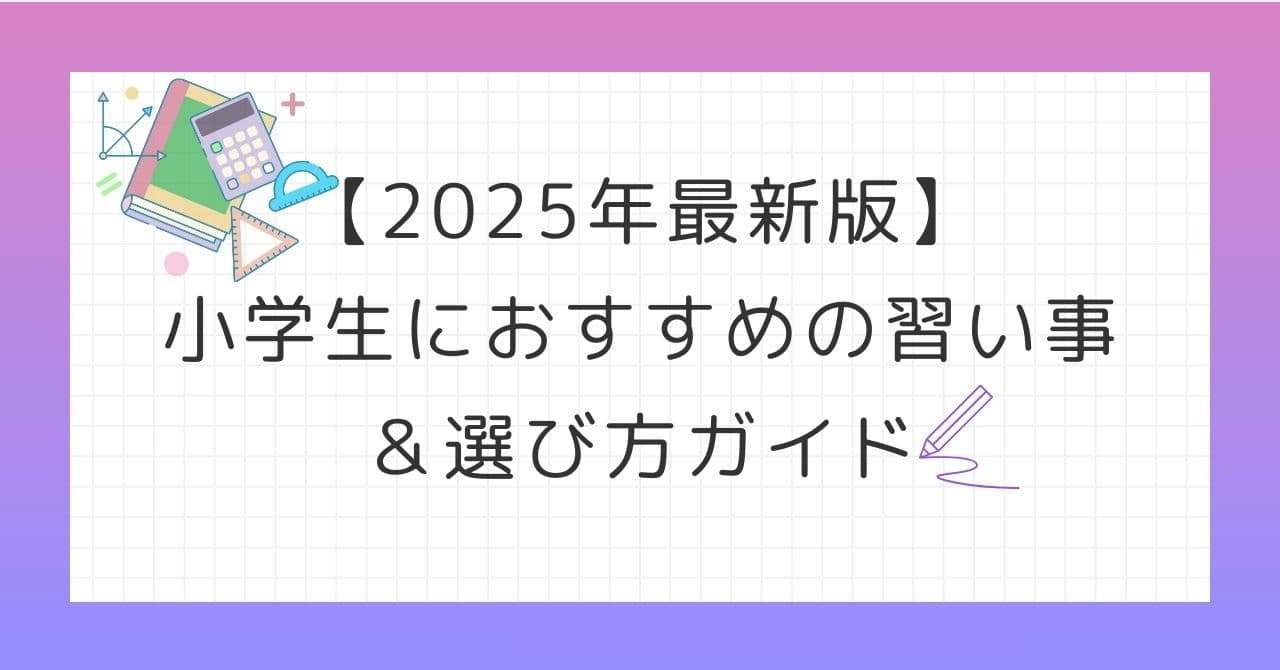「このままでいいのかな…」
まわりの子どもが次々に習い事を始めると、ふとそんな不安に駆られることはありませんか?
小学生の放課後をどう使うかは、成長や将来に大きく影響するテーマ。
でも焦って始めると、思わぬ落とし穴も。
この記事では、小学生の習い事について最新ランキング、ジャンル別の特徴、後悔しない選び方を徹底解説します。
ただし、本当に大切なのは意外にも――。
【2025年最新版】小学生におすすめの人気習い事ランキング総まとめ

小学生にとっての習い事は、単なる「お稽古」ではなく、将来の自己肯定感や社会性、学力にもつながる大切な経験です。
2025年の最新動向を見ると、運動系・芸術系・学習系などジャンルを問わず「子どもが楽しめるか」「続けられるか」が重視されています。
ここではジャンル別に人気の習い事をランキング形式で紹介しつつ、性別や将来の視点からもおすすめの選び方を紐解いていきます。
総合ランキングTOP10|運動・学習・芸術ジャンル別におすすめを紹介
2025年現在、小学生に人気の習い事は以下のような傾向にあります。
運動系では水泳やダンス、学習系ではそろばんやプログラミング、芸術系ではピアノや絵画が根強い人気です。
体力づくり・学力向上・感性育成と、子どもの成長に応じて選ばれています。
以下の総合ランキングは、複数調査をもとにした“親と子の満足度”と“継続率”に基づいたおすすめ順です。
| 順位 | 習い事ジャンル | 内容の特徴・おすすめポイント |
|---|---|---|
| 1位 | 水泳 | 全身運動+基礎体力の向上。男女ともに高い継続率 |
| 2位 | ピアノ | 音感・集中力・表現力の向上に効果。自宅練習もしやすい |
| 3位 | 英会話 | 小学校英語との親和性◎。オンライン教室も人気 |
| 4位 | 学習塾 | 中学受験・学力強化に直結。個別指導塾が人気上昇中 |
| 5位 | プログラミング | 論理的思考・創造性が育つ。低学年から対応可能 |
| 6位 | ダンス | 表現力と運動能力の両立。楽しく続けやすい |
| 7位 | 習字 | 字がきれいになるだけでなく、集中力も高まる |
| 8位 | サッカー | チームプレーと体力育成に◎。男児に特に人気 |
| 9位 | そろばん | 計算力UPと右脳活性化に効果。短時間レッスンも可能 |
| 10位 | 絵画・造形 | 自由な発想と感性の育成に。芸術系が得意な子におすすめ |
男の子・女の子別に人気の習い事|小学生におすすめの選び方ガイド
小学生の習い事選びでは、男女で興味関心の傾向に違いがありますが、近年はジェンダーレスな選択も増えています。
とはいえ、傾向としては以下のような“人気ジャンル”に分かれていることが多いです。
親が押しつけるのではなく、「子ども自身が楽しめるか」が最も重要なポイントです。
送迎のしやすさや自宅での取り組みやすさも考慮すると、習い事選びはグッと現実的になります。
1.英会話:ゲーム感覚のレッスンが多く、飽きずに学べる
2.サッカー:体を動かしながら仲間と関われる王道習い事
3.水泳:全身運動+達成感がある進級制度が魅力
4.プログラミング:ゲーム作り感覚で論理思考が伸びる
5.武道(空手・柔道など):礼儀と自信が身につく
1.ピアノ:感性と集中力を養う定番の習い事
2.英会話:発音やコミュニケーションを楽しく学べる
3.ダンス:音楽と動きを通して自己表現が育つ
4.習字:静かな環境で集中する時間が取れる
5.バレエ:姿勢・表現・柔軟性が身につく人気ジャンル
東大生・有名人が子どもの頃に通っていた“意外な”おすすめ習い事とは?
実は、東京大学の学生や各分野の著名人が幼少期に取り組んでいた習い事には共通点があります。
文部科学省や東大家庭教師の調査によると、「水泳」「ピアノ」「英会話」が3大定番で、どれも非認知能力(集中力・自己表現力・持続力)に強く関連しています。
特にピアノは、練習によって脳の前頭前野が活性化し、学習効率を高める効果があると言われています。
🧠 東大生が子どもの頃にしていた習い事TOP5(複数回答)
| 順位 | 習い事 | コメント・傾向 |
|---|---|---|
| 1位 | 水泳 | 習慣化・達成感・体力作りに貢献 |
| 2位 | ピアノ | 集中力・忍耐力・リズム感を育成 |
| 3位 | 英会話 | グローバル対応・発音習得に有利 |
| 4位 | そろばん | 計算力・記憶力・注意力を鍛える |
| 5位 | 習字 | 丁寧さ・集中・美的感覚を育てる |
習い事をしている小学生の割合と費用の最新データ
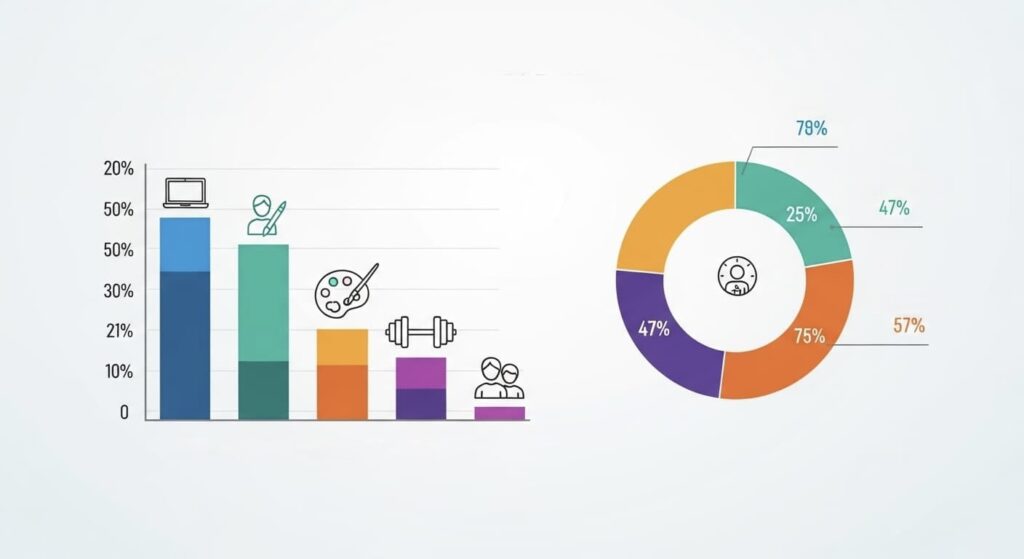
小学生の習い事事情は、家庭の家計や教育方針に直結する重要なテーマです。
どのくらいの割合で通っているのか?費用の平均や家庭ごとの違いは?という疑問にお答えします。
最新の統計データを使って、複雑な情報もすっきり理解できる形でご紹介します。
小学生の約7割が習い事に通っている理由とは?
6000以上の家庭を対象にしたFrankelの調査によると、約72.5%の小学生が習い事に通っていることがわかっています。
また、ニフティのアンケートでは約84.2%とさらに高い割合が報告されており、習い事はもはや小学生の生活の一部になっているといえます。
家庭側では「子供が続けたい」「将来に役立ちそう」といった理由が多く挙げられており、単なる習い事ではなく成長支援の手段とされていることが伺えます。
習い事にかける費用の平均と家庭ごとの差
小学生が習い事にかかる費用は、家庭や学年によって幅がありますが、ベネッセの調査によると、月平均16,676円というデータがあります。
一方、文部科学省などを出典とする調査では、公立小学生では年間約214,451円=月1.8万円、私立では年間646,889円=月5.4万円と、大きな開きがある傾向です。
さらに、ソニー生命の調査では、習い事・学習費含めた学校外教育費の平均額は月15,394円という結果もあり、一般家庭の支出はこのあたりが目安といえそうです。
公立・私立・地域別の違いも比較しよう
以下の表は、公立と私立、都市部と郊外で習い事にかかる特徴の差をまとめたものです。
家庭の教育方針や経済状況によって、選べる習い事や継続可能性が変わる点にも注意が必要です。
| 分類 | 月の平均費用(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 公立小学生 | 約18,000円 | 習い事費用の全国平均に近い値 |
| 私立小学生 | 約54,000円 | 大きな差、習い事の多さや高価格帯要因 |
| 共働き家庭 | — | 通える習い事の多様性が広がる傾向 |
| 年収300万円未満家庭 | — | 習い事をしていない割合が高い(69%以上) (リセマム) |
公立と私立でここまでの価格差がある背景には、受験対策塾や高級教室の選択肢、道具・制服などの初期費用の違いも大きく関係しています。
ジャンル別に見る!おすすめ習い事の特徴とメリット・デメリット
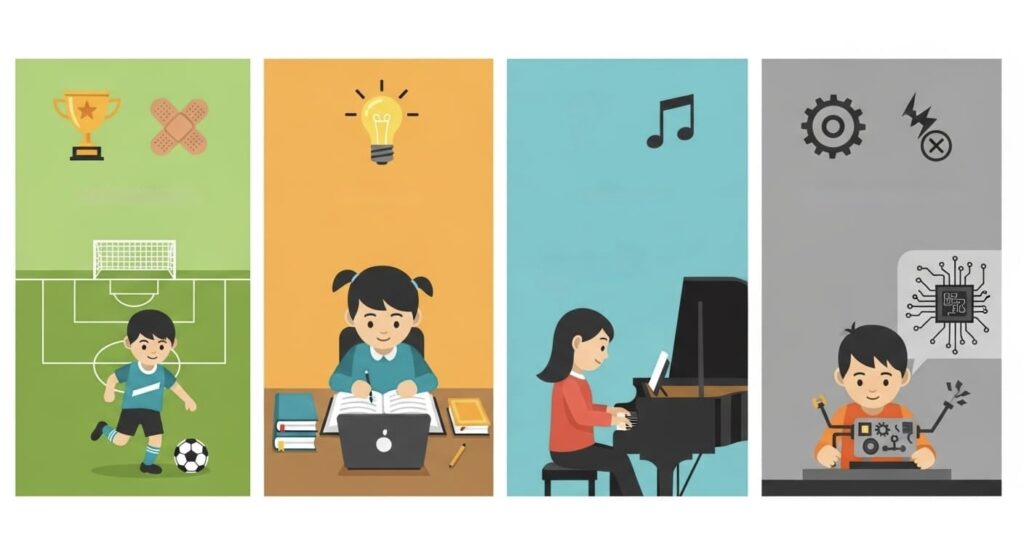
習い事にはジャンルごとに育てられる能力や求められる負担が異なります。
運動系・学習系・芸術系・将来性重視系の4ジャンルに分け、それぞれの特色と、おすすめできる点と注意すべき点を整理します。
あなたのお子さんの性格・興味・家庭の状況と照らし合わせて、無理なく続けられる習い事を選ぶヒントにしてください。
運動系のおすすめ習い事(スイミング・サッカー・ダンスなど)
●全身運動を通じて体力・柔軟性・持久力が育ち、健康維持に効果的。
水泳は呼吸器系や心肺機能の強化にもつながります。 ●チームスポーツ(サッカーなど)やダンスでは協調性・集団行動・他者との関わり方を学ぶ機会が豊富。 ●運動をすることでストレスを解消したり、日常とは異なる達成感を得られたりするため、自信を育てる習い事としておすすめです。
●発表会・試合・遠征などがあるジャンルでは、休日や移動時間の負担が増えることがあります。 ●ケガのリスクがゼロではなく、身体の発達段階や指導者・設備の安全性を確認する必要があります。 ●継続が必要なジャンルが多く、途中で飽きや負担を感じて辞めてしまうケースも。
月謝・用具・移動コストがかさむことも。
学習系のおすすめ習い事(塾・英会話・そろばん・プログラミングなど)
●学習塾では基礎学力・応用力が強化されるため、学校の成績アップや受験準備に直結することが多い。 ●英会話はコミュニケーション能力や発音・リスニング力を育て、将来的な国際化社会でも役に立つスキル。 ●そろばんは計算力だけでなく、集中力や暗算力・記憶力を鍛えることができ、「右脳・左脳の活用」が期待されます。 ●プログラミングは論理的思考や問題解決力を伸ばし、2020年以降の小学校プログラミング必修化の流れにも合致しています。
●学習塾やそろばんは宿題や復習が多く、家庭での時間が必要になるため共働き家庭ではスケジュール調整が重要。 ●英会話教室は教室によってレッスン時間・講師の質に差があるため、内容を見極めないとコスパが悪くなることも。 ●プログラミングやオンライン学習は教材やデバイスへの投資が必要で、月謝以外の初期費用・道具代がかかりやすい。 ●「即効性」が見えづらいジャンルゆえに、目に見える成果を求めるとモチベーション維持が難しいことがあります。
芸術系のおすすめ習い事(ピアノ・バレエ・書道・絵画など)
●感性・創造性が育ち、表現力や集中力・手先の器用さなど、学力以外の側面も豊かにする能力が鍛えられます。 ●美しい姿勢や礼儀作法、落ち着いた時間を過ごす習慣が身につくことがあり、生活全体の質が向上するケースも多い。 ●作品を作る経験や発表会などを通して達成感が得られる一方、自律性や継続力も養われる要素があります。
●発表会・舞台衣装・楽器等の道具の購入やメンテナンスなど、予想外の出費が発生することがあります。 ●バレエやピアノなどは専門的な指導が必要で、先生・教室の質によって差が大きく、通いやすさ・アクセスも重要。 ●芸術系は競争・評価・自己表現が絡むため、プレッシャーを感じる子どもには負荷になることがある。
将来性・スキル重視の新しい習い事(ロボット・STEAMなど)
●STEAM教育・ロボット教室では、科学・技術・工学・芸術・数学を融合させた学びが可能で、異分野の知識を統合する能力が育ちます。 ●問題解決力・創造性・論理的思考を養うことができ、将来AI技術が発展する社会で求められる素養を身につけることが期待されています。 ●プロジェクト型学習やワークショップ形式で体験を通すものが多く、子どもが主体的に取り組みやすい。
●専門講師や教材の質・量にバラツキがあり、それが学びの深さに直結するため、教室選びが重要。 ●月謝や教材・設備のコストが高めなケースが多く、家庭の予算と相談が必要。 ●伝統的な学習(国語・算数など)のような即効的な成果が見えづらいため、保護者の期待とのギャップが生じることもあります。
学年別|小学生におすすめの習い事とその理由

小学生の習い事は、学年ごとに発達段階や生活リズム、興味関心が大きく異なります。
学年に合わない習い事を選んでしまうと、子どもが負担を感じてしまうこともあります。
そのため、年齢や性格だけでなく、「今どんな力を伸ばしたいのか」「将来どんな選択肢を広げたいのか」といった視点からも考えることが大切です。
特に低学年では「楽しさ」や「基礎づくり」が重視され、中学年になると「集中力や継続力」が育ち始めます。
高学年になると「目的意識」や「将来像」とのつながりも重要になってきます。
以下では、各学年に応じたおすすめ習い事と、その理由について詳しく解説します。
低学年(1〜2年生)におすすめの習い事とは?
低学年は、好奇心が旺盛で何にでも興味を持ちやすい時期。
まだ学校生活にも慣れない時期のため、無理のないペースで通える習い事が理想です。
運動系では「スイミング」や「体操」が人気で、全身運動を通して基礎体力を養うことができます。
また、芸術系では「ピアノ」や「絵画教室」も集中力や表現力を楽しく育てるのに効果的です。
学習系では「そろばん」や「英会話」など、ゲーム感覚で楽しめる教材を使っている教室がおすすめ。
まずは「通うことが楽しい」と思える習い事を選ぶことが、長く続けるための第一歩になります。
| 順位 | 習い事ジャンル | 人気理由 | 推定通塾率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | スイミング | 体力向上・喘息対策・バランスの良い運動 | 約35〜40% |
| 2位 | ピアノ | 集中力・リズム感・耳を育てる | 約20〜25% |
| 3位 | 英会話 | 小学校の英語授業開始に合わせた準備 | 約18〜22% |
| 4位 | 体操 | 柔軟性・運動神経の基礎づくりに効果的 | 約15% |
| 5位 | そろばん | 計算力・集中力・暗算能力が自然に身につく | 約10〜12% |
中学年(3〜4年生)で伸ばしたい能力とおすすめの習い事
この時期は、集中力・理解力・人間関係の構築力がぐっと伸びるタイミングです。
小学校にも慣れ、ある程度の責任感や自立心が芽生えるため、「目標に向かって努力する力」を養える習い事がおすすめです。
たとえば、スポーツ系なら「サッカー」「ダンス」「剣道」など、仲間と協力しながら取り組むものが人気。
学習面では「プログラミング教室」や「読書・作文系」など、知的好奇心を刺激する習い事が注目されています。
習い事を通じて「好きなことを深める」「得意を見つける」ことができると、自信にもつながります。
| 順位 | 習い事ジャンル | 人気理由 | 推定通塾率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | スイミング | 継続者が多く、学校の水泳授業との相性も良い | 約38〜42% |
| 2位 | サッカー・野球 | 仲間との協調性・体力・戦術理解を深める | 約25% |
| 3位 | 学習塾(国算理) | 中学受験準備や苦手科目克服の目的での通塾 | 約22〜30% |
| 4位 | プログラミング教室 | タイピング・論理思考・創造力を伸ばす | 約15〜18% |
| 5位 | 英会話 | 英検対策やスピーキング力向上 | 約15% |
高学年(5〜6年生)から始める習い事の選び方
高学年になると、思考力・判断力が一段と育ち、習い事に対しても目的意識を持ち始めるようになります。
「中学受験」「部活動への移行」「将来やりたいこと」など、子ども自身が自分の未来を見据えて選択する機会にもなります。
この時期におすすめなのは、目的に合わせた習い事選びです。
受験を視野に入れるなら「塾」や「英検対策」「作文教室」などが選ばれやすく、スキル重視なら「ロボット教室」や「資格系の習い事」も人気です。
あえてこのタイミングで「新しい挑戦」を始めることで、学びに対するモチベーションも高まりやすくなります。
| 順位 | 習い事ジャンル | 人気理由 | 推定通塾率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 学習塾(中学受験含む) | 本格的な受験対策、内申対策としてニーズが高まる | 約40〜50% |
| 2位 | 英語・英検対策 | 中学進学後を見据えたスピーキング・読解力習得 | 約20〜25% |
| 3位 | プログラミング・ロボット教室 | 新しいスキル・論理的思考の育成 | 約18% |
| 4位 | スポーツクラブ系 | 運動習慣の維持や部活動へのスムーズな移行 | 約15% |
| 5位 | 書道・バレエ・芸術系 | 自己表現や集中力、感性の育成 | 約10% |
習い事を始めるおすすめのタイミングはいつ?

習い事を始めるベストな時期は、子どもの性格や家庭の状況によって異なります。
とはいえ「早すぎると続かない」「遅すぎると周囲に差を感じる」といった悩みは、どの家庭にも共通するものです。
ここでは、小学生からの習い事開始の目安や、子どもの興味・生活リズムに合ったタイミングの見極め方を、具体的に解説していきます。
小学生になってからでも遅くない?タイミングの目安
未就学のうちから習い事を始める子も増えていますが、小学生になってからのスタートでも決して遅くはありません。
実際、多くの習い事が「小学生コース」から本格的なカリキュラムを設けており、基礎体力・集中力・社会性が育ってくるこの時期は、吸収力も高まります。
特に1〜2年生はスタートに適した学年とされ、スイミングやピアノ、英語など、人気の習い事が無理なく始められる年齢です。
本人が「やってみたい」と前向きなら、どのタイミングでも遅すぎるということはありません。
続けやすい時期/やめやすい時期の見極め方
習い事は「始めるタイミング」だけでなく、「続けられるタイミング」も重要です。
たとえば、年度初め(4月)や学年の切り替え時(3月)は、気持ちがリセットされやすく、新しいチャレンジへのモチベーションも高まります。
一方で、夏休み明けや長期連休後はモチベーションが下がりやすく、やめたくなる時期でもあります。
子どもが疲れていたり、学校との両立が難しく感じている場合は、一時的な「中断」も視野に入れながら、家庭のスケジュールや本人の表情に注目するのがおすすめです。
子どもが「やりたい」と言ったときがベスト?
子ども自身が「やってみたい!」と意欲を見せたときは、まさにベストなタイミングです。
自発的な意欲こそが、継続力や学びの質に直結します。
とはいえ、SNSや友達の影響による一時的な興味の場合もあるので、すぐに申し込まず、体験レッスンや見学を通じて本気度を確認するのがおすすめです。
また、本人の「やりたい」と保護者の「続けてほしい」のギャップがあると、トラブルの元になります。
親子で話し合いながら選ぶことが、習い事を長く楽しむ第一歩となります。
習い事のメリットとデメリットを正しく理解しよう

「子どものために何かを始めたい」と思ったとき、まず候補に上がるのが“習い事”。
しかし、メリットばかりに目を向けすぎると、後から思わぬ負担や後悔が生じることもあります。
本章では、習い事の“いい面”と“気をつけたい点”を冷静に比較しながら、保護者としての選び方のヒントをお伝えします。
習い事がもたらす4つのメリット(自信・交友関係・将来性など)
習い事を通じて得られるメリットは多岐にわたります。
●自分でできることが増えることで自己肯定感が高まり、自信につながるという効果。
たとえば逆上がりができた、発表会で弾けた…といった小さな達成体験が子どもを成長させます。
●異なる学校や年齢の子と関われる機会が増え、学校以外の交友関係が育まれるのも魅力です。
●早期から特定の分野に触れることで将来の選択肢が広がる可能性も。
●受験や就職においても「継続力」「スキル」が評価される時代において、習い事で培った力は強みとなるでしょう。
親が知っておきたい3つのデメリット(費用・送迎・過密化)
一方で、保護者にとって現実的な悩みもあります。
1つ目は、費用負担。
月謝に加えて教材費や発表会費などが重なると、年間で10万円以上になるケースも珍しくありません。
2つ目は、送迎や付き添いの負担。
共働き家庭では平日夕方の移動や兄弟間の調整が大きなストレスになることも。
3つ目は、スケジュールの過密化。
放課後や休日に予定が詰まりすぎて、子どもが「遊ぶ時間がない」「疲れやすい」と感じることもあります。
このようなデメリットも事前に理解しておくことで、選び方や運用の仕方が変わってきます。
| 習い事のメリット・デメリット比較表(2025年版) | ||
|---|---|---|
| 視点 | メリット | デメリット |
| 子ども | ・自信がつく(達成体験)
・友だちが増える ・将来のスキルにつながる |
・疲れやすい(スケジュール過密)
・「やらされ感」でモチベ低下することも |
| 保護者 | ・子どもの可能性を伸ばせる
・教育的な時間活用ができる |
・費用がかさむ(年10万円以上も)
・送迎や付き添いの負担が増える |
| 家庭全体 | ・生活にリズムができる
・兄弟姉妹で協力のきっかけになる |
・家族の時間が減る
・他の予定とバッティングしやすい |
メリットを最大化しデメリットを減らす方法
習い事の良さを引き出し、負担を減らすには“取捨選択”がカギです。
まずは家庭の方針と子どもの興味をしっかり擦り合わせることが前提。
流行や他の子に合わせて始めるのではなく、子どもが本当に関心をもって取り組めるものを1〜2個に絞りましょう。
また、通いやすさや曜日・送迎のしやすさも重要なチェックポイントです。
最近では「オンライン英会話」や「土曜日だけのプログラミング教室」など、柔軟なスタイルも増えています。
“無理のない範囲で楽しめる”ことが、最終的に続ける力につながり、メリットを最大限に活かす秘訣です。
習い事選びで後悔しない!おすすめのチェックポイント5選

小学生の習い事は、ただ「通うこと」が目的ではなく、継続して成長につなげることが重要です。
ところが実際には「途中でやめてしまった」「親子でストレスになった」という声も多く聞かれます。
習い事選びに失敗しないためには、子どもの性格・家庭の状況・将来の展望をふまえた“総合的な視点”が求められます。
ここでは、実際に後悔した家庭の声や成功例も交えながら、特に重要な5つのチェックポイントを紹介します。
子どもが「楽しい」と感じるかが最優先
子どもにとって習い事は「学びの場」であると同時に、「遊びに近い喜びの場」であることが理想です。
親が「英語は将来役立つ」「ピアノをやらせたい」と願っても、子ども自身が心から楽しめないと継続は困難になります。
特に低学年では、動機づけや興味の芽生えが習い事の質を大きく左右します。
たとえば「工作好きの子がロボット教室にハマった」「友達がいるからダンスが続いている」など、本人の好奇心が原動力となった例は多くあります。
無料体験や見学を必ず取り入れ、「やらされている感」がないか観察することがカギです。
通いやすさ・送迎のしやすさも忘れずに
どれほど良い内容の教室でも、「通うのが大変」であれば習慣化しづらくなります。
実際、習い事の離脱理由で多いのが「送迎が負担になった」「帰宅が遅くなりすぎた」というもの。
共働き家庭では特に、親のスケジュールに無理が出ない範囲での選定が重要です。
送迎バスの有無や、学童との連携、兄弟の同時受講なども検討材料になります。
また、最近はオンラインやハイブリッド型の習い事も増えており、自宅で学べる「プログラミング教室」や「オンライン英会話」も人気です。
「移動がない」ことが親子の時間的ストレスを減らす大きな利点になります。
教室の雰囲気や先生との相性を確認しよう
「先生との相性」は、子どものやる気や安心感に直結します。
実際、先生の声かけひとつで「やる気が出た」り「緊張して黙ってしまう」など反応が大きく分かれることも。
たとえば「褒めて伸ばすタイプ」「厳しめでペース重視」など指導スタイルは様々で、子どもの性格に合うかどうかが継続のカギとなります。
また、教室の雰囲気も見逃せません。
アットホームで少人数制が向く子もいれば、活気がある集団型が刺激になる子もいます。
口コミだけで判断せず、体験時の子どもの表情や帰宅後の感想から“本音”をくみ取ることが大切です。
先生の指導歴や資格など、信頼できるプロかどうかもチェックしておきましょう。
家計に無理のない範囲で費用を見積もる
習い事の費用は月謝だけでなく「入会金・教材費・道具代・発表会費」なども含めて考える必要があります。
特にピアノ・バレエ・水泳などは年間で数十万円に達することもあり、知らずに契約して後悔する家庭も。
経済的に無理があると、子どもに不安を与えたり、ほかの習い事を諦めざるを得なくなるケースも出てきます。
また、「高ければ良い」という先入観も注意が必要です。むしろ“価格に見合う中身か”“家庭にとって続けやすいか”を基準にしたいところ。
複数の教室を比較したり、兄弟割・紹介割などの制度を活用することで、より無理のないスタイルを見つけることができます。
柔軟なスケジュールや振替制度も要チェック
小学生は風邪や学校行事、家庭の都合などで突然休まざるを得ないことが頻繁にあります。
そのたびに「振替不可」や「キャンセル料が発生する」教室だと、ストレスが積み重なり親子ともに疲弊してしまいます。
最近では「月内なら何回でも振替可能」「アプリでスケジュール変更可能」といった柔軟な対応をしてくれる教室も増えており、非常に好評です。
特に共働き家庭にとっては、予定の組みやすさ=継続のしやすさ。
土日開催、兄弟別曜日受講、オンライン併用など、柔軟性のある教室を選ぶことで、途中で辞めてしまうリスクも軽減されます。
| 習い事選びのチェックリスト表 | |
|---|---|
| チェック項目 | 内容の確認ポイント例 |
| ✔ 子どもが楽しんでいるか | 無理に行かせていないか/帰宅後にポジティブな感想が出ているか |
| ✔ 通いやすい立地・スケジュールか | 自宅・学校から通いやすい距離か/送迎に無理がないか/振替制度があるか |
| ✔ 先生や教室の雰囲気が合っているか | 子どもの性格と先生の指導スタイルが合っているか/教室の雰囲気に安心感があるか |
| ✔ 家計に無理のない費用か | 月謝以外の費用(教材・イベントなど)も含めて想定範囲か |
| ✔ 継続できそうな環境か | 子どもが飽きていないか/学年が上がってもスケジュール的に無理が出ないか |
【体験談】習い事をやってよかった!保護者のリアルな声

習い事は「将来のために…」という目的で始められることが多いですが、実際に通わせてみると親が思いもしなかった成長が見えることも。
ここでは実際に習い事を経験した保護者の声を紹介し、良かった点や反省点、忙しい家庭での工夫などを掘り下げます。
「自己肯定感が上がった」「学校外の友達ができた」
【体験談】ピアノとサッカーを続けたことで、自信がついた小3男子の例
「最初は人前で話すのも苦手だった息子が、発表会で演奏を終えた後、満面の笑みで“楽しかった”と言ってくれました。」
「試合でゴールを決めたときも、知らない子とも自然と会話していて…。“できた”体験が増えることで、自分を認められるようになったのだと思います。」
● 習い事は、「家庭・学校以外のつながり」や「成功体験」を増やす貴重な場
● 自分の得意分野を見つけたことで、自信が日常生活にも波及
● 他学年や異なる学校の友達との関わりで、対人スキルも自然と育つ
「通わせすぎて失敗した…」反省から学ぶ3つのポイント
| 反省点 | 実際の声(保護者より) | 解決策 |
|---|---|---|
| スケジュールが過密だった | 「週5で通わせたら本人が疲れて泣くように」 | 週2〜3回までに抑え、“自由時間”を確保 |
| 子どもの意思を尊重しなかった | 「友達がやってるからと無理にピアノを始めたが結局嫌がった」 | 体験教室で本人の反応を確認してから検討する |
| 家計への負担が想定外だった | 「月5万円を超えて見直しを余儀なくされた」 | 費用上限を決めて習い事を選ぶ(1万円以内など) |
教訓:長く続けるには「本人の意思」と「生活全体のバランス」を優先すべき。
見直しのタイミングも重要です。
共働き家庭での習い事スケジュール管理のコツ
【リアル事例】共働き夫婦(子ども:小2女児)の工夫
「うちはカレンダーアプリで“送迎当番”を管理し、平日は週2回までと決めています。
通える教室が限られるので、“駅近+振替可能”を条件に選んでいます。
日曜は子どものリクエストで公園遊びにして“無習い事日”に。」
● GoogleカレンダーやTimeTreeで家族全体の予定を共有
● 送迎が難しい日は“自習型”や“オンライン型”も活用
● ファミサポや祖父母の協力も事前に相談しておく
● 習い事は「詰め込むもの」ではなく「生活に馴染むもの」を基準に選ぶ
● “習わせない日”も予定に組み込むことで、子どもの気力と体力の余白を確保
無料〜1,000円台も!おすすめ体験レッスンの活用術

子どもの習い事を始める前に、まずは「体験レッスン」からスタートするのが定番です。
最近は無料〜1,000円程度で参加できる体験会も多く、失敗リスクを抑えながら子どもに合うかどうかを判断できます。
ここでは、体験を活用するメリットや注意点、全国で受けられる人気サービスまで紹介します。
初めての習い事は「体験あり」が安心な理由
初めての習い事は、実際にやってみないと「合う・合わない」がわかりません。
体験レッスンを活用することで、子ども自身が楽しめるかを感覚的に判断できるうえ、保護者も教室や先生の雰囲気を事前に把握できます。
また、入会後のミスマッチを防ぎ、時間・費用の無駄を省く効果も。
複数体験を経てから比較検討するのがおすすめです。
体験レッスンでチェックすべき5つのポイント
体験レッスンの参加時は、以下のポイントを意識しましょう。
| チェックポイント | 内容の確認例 |
|---|---|
| ① 子どもの反応 | 楽しんでいたか?嫌がらずに集中できていたか? |
| ② 講師の対応・相性 | 優しく声かけしてくれる?距離感はどうか? |
| ③ 教室の雰囲気 | 安全性・清潔感・他の生徒の様子はどうか? |
| ④ カリキュラムの明確さ | どんな目標を持って進めていくのかが説明されたか? |
| ⑤ 通いやすさ・送迎の手間 | 家からの距離や時間帯、振替制度は整っているか? |
これらを総合的に見て、「また来たい」と子どもが言うかどうかが最大の判断基準となります。
全国対応!体験レッスン付きおすすめサービス一覧
以下は、全国または主要都市で体験レッスンを実施している代表的な習い事サービスです。
いずれも無料または1,000円未満で気軽に参加できます。
| サービス名 | ジャンル | 体験費用 | 対象年齢 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ベネッセこども英語教室 | 英会話 | 無料〜500円 | 3歳〜小学生 | 大手教材会社による安心の運営 |
| カワイ音楽教室 | ピアノ・リトミック | 500円前後 | 1歳〜小学生 | 全国展開、柔軟なレッスン内容 |
| ロボ団 | ロボット・STEAM | 無料 | 年長〜小学生 | 初心者でも楽しめるプログラミング体験 |
| スイミングスクール(各地) | 水泳 | 無料〜1,000円 | 4歳〜小学生 | 多くが1回体験レッスンあり |
| プログラミングキッズ | プログラミング | 無料 | 小1〜小6 | 通信型や教室型から選べる |
よくある質問Q&A|習い事に関する親の疑問を解決

子どもの習い事について、保護者の間では「何個まで?」「男女で違う?」「お金のサポートはある?」といった具体的な疑問がよく聞かれます。
ここでは、特に多い3つの質問に丁寧にお答えします。
Q. 小学生に習い事はいくつが理想?
A:1〜2つがベスト。
多くても3つまでが無理のない範囲です。
文部科学省や教育機関の調査でも、平均は約1.5個。
小学校低学年では「1つ」、中学年以降は「2つ」程度が目安とされています。
やりすぎは疲労や勉強への悪影響につながることも。
| 学年 | 理想の習い事数 | 補足 |
|---|---|---|
| 低学年(1〜2年) | 1つ程度 | 放課後の自由時間も重視 |
| 中学年(3〜4年) | 1〜2つ | 学習+運動などのバランス型が人気 |
| 高学年(5〜6年) | 2〜3つまで | 将来に向けたスキル習得も意識 |
Q.男の子と女の子で向いている習い事は違う?
A:違いはありますが、性別より「個性・興味」を尊重しましょう。
一般的に、男の子は運動系・プログラミング、女の子はピアノ・英会話・バレエなどに人気が偏りがちです。
しかし、最近は男女問わずSTEAMや英会話など、ジェンダーレスな習い事が広がっています。
| 人気の傾向(参考) | 男の子に人気 | 女の子に人気 |
|---|---|---|
| 運動系 | サッカー、空手、野球 | ダンス、体操、バレエ |
| 学習系 | プログラミング、そろばん | 英会話、学習塾、国語教室 |
| 芸術・スキル系 | ドラム、工作、囲碁 | ピアノ、習字、絵画 |
Q.習い事の補助金・助成制度は活用できる?
A:自治体や一部企業・NPOなどの制度があり、活用可能です。
実はあまり知られていませんが、市区町村単位での助成制度や、子育て支援策の一環として一部費用の補助を行う自治体があります。
特に生活保護世帯・ひとり親世帯には手厚い制度も。
| 補助制度の例 | 内容 |
|---|---|
| 就学援助制度(自治体) | 習字・そろばん等、学習活動に関する補助(要申請) |
| こども未来サポート制度など(NPO) | 習い事費用の一部または全額をサポート |
| 地域の子ども食堂・放課後教室 | 無料で学習やアート体験などを提供している場合も |
関連コラム
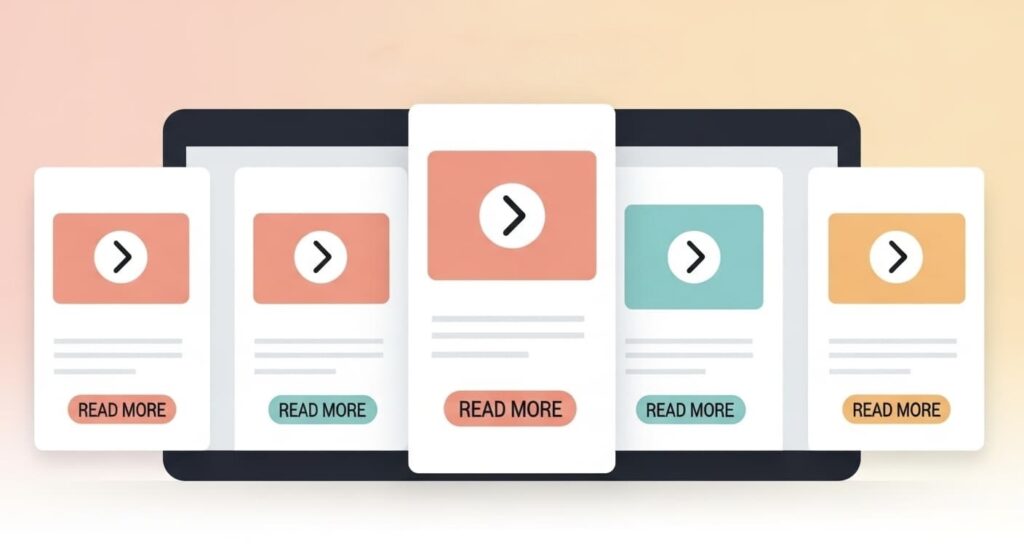
| 記事タイトル | 内容の概要 |
|---|---|
| 幼児教育×非認知能力の決定版|年齢別アプローチと遊び・習い事の選び方 | 非認知能力(自己肯定感・協調性・やる気など)の重要性に着目し、家庭と園との連携や遊びを通じた実践アイデアが豊富に紹介されています (心理学で紐解く、私の物語)。 |
| 幼児教育における「遊び」の重要性とは?年齢別・発達段階別の選び方から実践方法まで | 「遊び=学び」をテーマに、脳科学・心理学の視点から、年齢に合った遊びの選び方や家庭での取り入れ方を具体的事例と共に解説しています (心理学で紐解く、私の物語)。 |